藤堂高虎と言えば、何度も主君を変えて出世した人物として、マイナスイメージを持たれがちです。しかし、豊臣秀長には秀長の死去まで15年、後継者・秀保にも秀保の死去まで仕えました。それだけではなく、秀長の没後は江戸時代まで秀長の法事を営み続けます。また、江戸時代に秀保の母親との交流が見られます。豊臣秀長・秀保への想いを忘れなかった高虎についてお話します。
藤堂高虎と豊臣秀長・秀保
高虎が何度も主君を変えたとして悪い印象を持たれがちであることと、実はそんなことはないということを以前にお話ししました。
高虎は21歳までは浅井長政→阿閉淡路守(貞征か)→磯野員昌(員昌養子で後継者の織田信澄を含む)→木下秀長(豊臣秀長、秀吉の弟)と主君を次々に変えました。しかし、21歳からは豊臣秀長に仕え続けました。
秀長には、その死去まで15年仕えました。秀長は最終的に大和国等に所領を持ち、大和郡山城を本拠にしたため、大和豊臣家と呼ばれます。秀長の死去まで仕え続けたということは、高虎にとって秀長は良い(理想の?)主君だったのでしょう。高虎も秀長のもとで出世していきました。
秀長の没後は養子の秀保(有名な関白豊臣秀次の弟、秀吉の甥)が跡を継ぎますが、秀保は若くして亡くなります。秀保の死去により、後継者不在となって、大和豊臣家は断絶します。
高虎は当時40歳でした。秀長・秀保への恩義や悲しみのためか、出家して高野山へ行きます。しかし、1ヶ月後には秀吉に呼び出され、伊予で7万石の大名となります。
その後は秀吉のもと、朝鮮出兵等で活躍します。そして秀吉没後は家康に急接近し、江戸幕府の草創期に幕府を支えて活躍することとなるのです。
江戸時代にも秀長の法事を継続
さて、高虎が大和豊臣家への恩義を忘れなかった証拠と考えられる事は次の2つです。
①秀長の法事を江戸時代まで継続して実施したこと。
②秀保の母と交流し、経済援助も申し出ていたこと。
まずは1点目を見ていきます。
秀長の菩提寺は、有名な京都の大徳寺の塔頭(たっちゅう。寺の中にある小さな寺のようなもの。)である大光院です。大光院は当初は大和国郡山(大和豊臣家の本拠地)にありましたが、高虎が大徳寺へ移転させたと言われています。
高虎はこの大光院へたびたび参拝したり、ここで秀長の法事を実施したりしています。史料で確認できるのは以下のとおりです。
- 慶長10(1605)年、法事(『鹿苑日録』)
- 慶長11年、参拝(『高山公実録』)
- 慶長12年、法事(『高山公実録』)
- 慶長18年、参拝(『高山公実録』)
- 元和元(1615)年、参拝(『高山公実録』)
- 元和3年、法事(『高山公実録』)
- 元和5年、法事(『高山公実録』)
- 元和9年、33回忌に際し、大光院へ作善料を贈る。大光院から修復願が出される(『高山公実録』・『公室年譜略』)
- 寛永2(1625)年、元和9年の大光院からの修復願に対し、修復を行う(『高山公実録』・『公室年譜略』)
- 寛永3年、子の高次・高重と一緒に参拝(『高山公実録』・『公室年譜略』)
どうですか?この回数。関ヶ原の戦い以降、高虎の死去まで30年で10回です。
江戸時代になると、幕府の目がある以上、諸大名は豊臣家寄りの行動は難しくなったと思います。慶長20(元和元・1615)年に豊臣家が滅亡した後はなおさらです。
しかし、高虎は幕府に構わず?大光院への参拝や法事を続けます。幕府がこれをどのように思っていたのか?幕府の信頼の厚い高虎だから黙認された、というのはさすがに甘い気がします。
もしかしたら、秀長は家康と関係が良好であったとも言われることや、大和豊臣家は秀吉生前に断絶した(江戸幕府が滅ぼした家ではない)ことで、幕府もそれほど神経を尖らせていなかったのでしょうか。そのあたりの理由はわかりません。
とはいえ、大和豊臣家も秀吉・秀頼の一族です。江戸幕府に忠節を尽くしながらも、秀長の菩提を弔い続けた高虎は、主君への恩義を忘れることの無い人物であると思います。
最後の参拝記録である寛永3年(高虎死去の4年前)には、高虎は子の高次・高重と一緒に参拝しています。(記録上では)最初で最後の子と一緒の参拝です。これが高虎最後の参拝になるであろうと予感し、子に「秀長への恩義を忘れるな」と言い聞かせているようです。
秀保の出自
次に、2点目の秀保の母との交流と経済援助について見ていきます。
秀長の養子秀保は、天正7(1579)年に秀吉の姉・ともと三好吉房の間に生まれたとされています。しかし、ともの年齢から、実際は養子であった可能性が指摘されています。実子か養子かはともかく、兄には後の関白秀次と、秀吉の養子となった秀勝(後に徳川秀忠正室となる江の2人目の夫)がいます。
余談ですが、高虎は秀保の兄・秀次と一緒に茶会に出席する(「宗及茶湯日記 自会記」)、秀次が高虎の屋敷を訪れる(「駒井日記」)等の交流が見られます。
秀保の相続と早すぎる死
秀保は天正16(1588)年に秀長の養子となります。同18年の小田原北条氏攻めにも出陣し、同19年の秀長の死去により、大和豊臣家を継ぎます。この時の秀保はまだ数え13歳で、家臣の高虎らが補佐しました。
天正20年には権中納言となり、大和中納言と呼ばれました。同年、朝鮮出兵(文禄の役)で出陣し、肥前国名護屋まで赴きました。
しかし、文禄4(1595)年、17歳の時に亡くなります。外出中、家臣が突然秀保を抱きかかえて崖の上から飛び降りたという逸話もありますが、当時の史料からは疱瘡による病死と考えられています。
秀保には子がおらず、大和豊臣家はこれをもって断絶となります。高虎はその後、秀吉に召し出されて大名となり、秀吉没後は家康のもとで活躍します。
秀保の母・日秀との交流
時代は進み、江戸時代の話になります。江戸時代にも高虎が秀長の法事を継続的に行っていたことは前述のとおりです。それとともに、高虎と秀保の母・とも(出家して日秀)の交流が見られるようになります。具体的には次のとおりです。
※この後登場する九条幸家は公家で、関白も務めた人物です。高虎とも親しく交流していたことが史料からわかっています。
- 元和6(1620)年、日秀が高虎に会うため、九条幸家を訪問する(この日、高虎も九条家を訪問)。
- 元和9(1623)年、九条幸家が日秀に使者を送り、後日、高虎が来るので日秀も来るように伝える。高虎も日秀に会いたいと幸家に伝える。2日後には実際に高虎・日秀が九条家を訪問。会った翌日、高虎は日秀へ毎年米100石を献上すること申し出る。
- 寛永2(1625)年、九条幸家が「瑞竜寺殿」からの贈り物を高虎へ渡す。日秀が建立した寺が瑞龍寺であることから、「瑞竜寺殿」=日秀とみられる。日秀は約半年前に死去しているため、その遺物として渡された可能性がある。
※根拠史料はいずれも『幸家公記』です。
いかがでしょうか。江戸時代になって約20年後、秀保死去からは約25~30年後の出来事です。この時期になっても高虎と日秀の交流があったことには驚きます。秀保死後からずっと交流が続いていたのか、この頃に交流が始まったのかは定かではありません。
しかし、高虎は毎年米を献上するという経済援助を申し出ています。これは秀保の母であるが故ではないかと想像します。十分にはできなかった旧主君・秀保への奉公の代わりに、その母・日秀に少しでもできることをしようと思ったのかもしれませんね。
秀長の法事とともに、秀保の母への援助。これらを見ると、高虎の人生にとって大和豊臣家がいかに重要な存在であったかがわかる気がします。高虎は、離れた主君を忘れてしまうような薄情な人物ではなかったのです。高虎への評価、もう少し考え直してはどうかな?と思います。
《参考文献》
- 「宗及茶湯日記 自会記」(千宗室編『茶道古典全集』第8巻、淡交社、1977年)
- 『鹿苑日録』第4巻(続群書類従完成会、1991年)
- 藤田恒春校訂『増補駒井日記』(文献出版、1992年)
- 『高山公実録』上巻・下巻(清文堂出版、1998年)
- 宮内庁書陵部編『図書寮叢刊 九条家歴世記録』4・5(明治書院、1999・2018年)
- 『公室年譜略』(清文堂出版、2002年)
- 藤田恒春『豊臣秀次』(吉川弘文館、2015年)


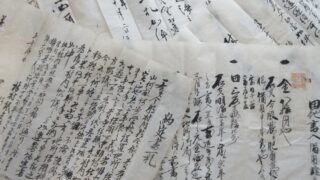


コメント