「中世墓(ちゅうせいぼ)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?その名のとおり、中世の墓地です。中世とは鎌倉~室町時代を中心とした時代です。中世に墓地として使用されたものの、現在は使われておらず、遺跡として残っている所があります。
では、中世墓は当時どんな風景だったのでしょうか?中世墓は発掘調査されることはありますが、長年使われていなかったため、当時の雰囲気を感じられないことが多いです。
今回は、そんな中世墓の中で、三重県菰野町にある杉谷中世墓を紹介します。ここは崩れていた墓石を積み直してはいますが、本物の墓石で、当時の雰囲気を感じられる場所です。
杉谷中世墓へのアクセス
杉谷中世墓があるのは三重県北部の菰野町杉谷です。工場夜景で有名な四日市市から見ると北西にあたります。
近鉄四日市駅から菰野町の湯の山温泉駅までを結ぶ近鉄湯の山線に乗れば、菰野町南部(パラミタミュージアムやアクアイグニスがある地域)へは行けます。ただ、杉谷中世墓のあたりは菰野町北中部になるので、電車だけで行くのは難しいです。
ということで、今回は車での行き方です。新名神高速道路の菰野インターチェンジのすぐ南東、国道306号線沿いに菰野町役場があります。ここからスタートします。
役場前から国道306号線を北上します。朝明川を越え、しばらく進むと杉谷川という小さな川を越えます(下のグーグルストリートビュー参照)。
橋を越えて2つ目の交差点(下のグーグルストリートビュー参照)を左折し、集落へ入って行きます。
かなり細い道になりますが、奥までどんどん進みます。右手にお寺が見えますが、まだ直進です。しばらく進むと右手に神社(熊野神社)が見えます。ここに広い駐車場があるので、車を停めさせてもらいます。

車を降りて、進んできた道を更に奥へ進みます。少し進むと、左側に「杉谷遺跡→」の看板があるので、ここからフェンス沿いに山へ向かって進んでいきます。

この先は所々に同じような案内板があるので、迷わずに行くことができます。
山に入りかけの所で小さな沢を渡ってすぐの看板の下、早くも墓石の一部があります(下の写真の矢印の石)。

-1024x768.jpg)
これは、後ほど紹介する五輪塔の部材です。右側の写真が拡大したものですが、左から、空風輪・水輪・火輪(裏返し)です。ここから墓地まではかなり距離があるのですが、このあたりにもかつて墓地があったのでしょうか。
山の中に入ってしばらく上り、坂がなだらかになった辺りからは、左右に平らに整地された区画が段々になって残っています。かつては寺院の建物等があった可能性があります。

例えば上の写真では、矢印の所に段があり、上の区画と下の区画に分かれています。どちらの区画も整地されたように平らになっています。
このあたりの看板のそばにも五輪塔の水輪が落ちています。

-1024x768.jpg)
ここから更にしばらく進むと、右へ曲がるように案内板があります。ここから右上を見ると、墓石(五輪塔)が林立しているのが見えます。これが杉谷中世墓です。

右へ曲がると、坂の上に説明板があります。

説明板の所から折り返して坂を更に上ると、いよいよ杉谷中世墓が目の前に広がります。


後述のように、実はこれらの墓石は発掘調査後に積み直されたものが多く、必ずしも当時積まれたままではありません。しかし、墓石は本物であり、中世墓がどんな風景であったのかを感じることができます。
杉谷中世墓とは
杉谷中世墓は、杉谷集落の西方約500mの丘の雑木林の中、高さ1mほどの土手の上に3ヶ所の区画があり、南北約40m、東西約25m、高さ約5mの斜面が墓地となっています。
杉谷中世墓はその名の通り中世の墓地で、鎌倉時代初期から室町時代末期まで使用されたと考えられています。昭和38年と同40年に発掘調査が行われ、同45年には三重県指定史跡となっています。
出土したのは五輪塔(後ほどの写真参照)124基、五輪塔の破片17基、一石五輪塔(本来は複数の部材で造る五輪塔を1個の石で造ったもの)34基、石仏4基、宝篋印塔(後ほどの写真参照)1基です。
現在は墓石が林立していますが、元々は土に埋まっていました。しかし、墓石の一部が崩れて付近の水田に落下したことがきっかけとなり、墓地が発見されました。現在立っている墓石は、発見後に積み直されたものです。
この場所は東向きの斜面で、山の東にある集落を一望できるような場所を選んだと考えられています(現在は雑木林の中なので、東を見ても集落は見えない)。
墓地の南西部の高い部分には火葬で使用した複数の穴(火葬穴)が残っています。現在はプレハブで覆われており、ガラス越しに見ることはできますが、光の当たり具合によってはガラスの反射で見づらいかもしれません。
火葬穴からは竹や薪、木棺の焼け残りや釘、銅銭が見つかっています。ここで火葬し、収骨後にこの墓地に埋葬したと考えられています。この墓地では土葬した痕跡は無いようです。
お墓の形状としては、1ヶ所ごとに約1m四方の穴が掘られ、深さは約30~40㎝となっています。穴の中心に蔵骨器(遺骨を納めた壺など)を埋め、その周りに握り拳ぐらいの石を敷き詰め、その上に五輪塔を立てています。
土の中からはその蔵骨器が多数発掘されています。杉谷中世墓では蔵骨器として壺・甕(かめ)等が使用されました。これらの壺等の産地は隣の愛知県にある瀬戸・常滑や岐阜県東部が主です。時期は12世紀末~16世紀前半で、13~14世紀が中心です。前述の、墓地が使用された時期(鎌倉時代初期から室町時代末期まで)は、この出土物から推定されたものです。
杉谷中世墓の墓石
では、この杉谷中世墓にどのような種類の墓石があるのかを見てみましょう。発掘された墓石の種類(五輪塔等)・数は前述のとおりです。
①五輪塔
五輪塔は4つの石を積み上げたものです。上から、先端が少し尖った半球形の空輪(くうりん)、お椀のような形の風輪(ふうりん)、屋根の形の火輪(かりん)、球形の水輪(すいりん)、直方体の地輪(ちりん)となっています。
空輪と風輪は1つの石となっており、火輪・水輪・地輪はそれぞれ別の石です。
空風火水地とは、密教において宇宙を構成するとされる要素です。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
杉谷中世墓で見られる五輪塔の高さは概ね50㎝程度です。それほど大きくはありません。世の中には2mを超す五輪塔もあるので、それに比べると小型でしょう。
②一石五輪塔
一石五輪塔は、本来は4つの石で造られる五輪塔を1つの石で造ったものです。そのため、「一石五輪塔」の名前があります。空輪~地輪の形は五輪塔と同じです。
下の写真は杉谷中世墓のものではありませんが、一般的な一石五輪塔です。

ここ杉谷中世墓では、かなり形が簡略化された一石五輪塔が多くあります。空輪~地輪の形は殆ど省略され、各輪の境目が少し溝状に彫られているだけのものもあります。
-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
③宝篋印塔
宝篋印塔は、本来はこの石塔の中に宝篋印陀羅尼というお経を納めた塔です。後の時代には墓石としても使用されました。杉谷中世墓に完全な形で残っている宝篋印塔はありませんが、本来は右の写真のような形をしています。
下から順に、変わった形の掘り込みがある「基礎」、記号のようなもの(梵字)が彫られている「塔身」、屋根のような「笠」、笠の上にある「相輪」からできています。

杉谷中世墓にあるのは一部の部材です。
-768x1024.jpg)
上から、相輪と笠があります。笠の下には塔身のようなものがありますが、明らかに大きすぎてアンバランスであることと、成形具合からすると塔身かどうかは判断しかねます。
④石仏
石仏はその名のとおり、石で造られた仏です。よく見られるのは道端にあるお地蔵さん(地蔵菩薩)でしょう。地蔵菩薩以外にも阿弥陀如来・大日如来・観世音菩薩(観音さん)等があります。
杉谷中世墓には石仏は少なく、仏像の形がわかるのは1つぐらいです。
-768x1024.jpg)
他には仏像の形を薄く彫ったものがありますが、顔が辛うじてわかる程度です。
-1-768x1024.jpg)
-768x1024.jpg)
周辺にも墓石が散在
現在の杉谷中世墓といえばこの墓石が多数林立している区画がメインですが、実は説明板の裏、北東の斜面を少し下りた所にも五輪塔の部材が点々と散在しています。
-1-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
このあたりまで墓地があったのでしょうか?もしくは、先ほどのメインの区画から斜面ごと崩れてきたとも考えられます。
メインの区画に至る前に、右へ曲がる看板がありましたが、曲がらずに少し直進した所にも五輪塔の部材が落ちています。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
これはメインの区画の南側斜面の下にあたるので、恐らく崩れてきたものでしょう。
ここへ来るまでにも道の途中に五輪塔の部材が落ちていましたが、そこに墓地があったのか、あるいは五輪塔が少し置かれていたのか。まだ杉谷中世墓はわからない事がありそうです。
なお、今回は紹介していませんが、杉谷中世墓の北東の谷を挟んだ山には寺の跡地があります。車を停めた熊野神社は熊野信仰に関係する所です。この辺りは広範囲にわたって神社・寺院・墓地が存在する霊場のような場所だったのかもしれません。
※記事の内容は2025年3月時点のものです。
《参考文献》
- 『菰野町史』上巻(三重県三重郡菰野町、1987年)
- 佐々木一「杉谷中世墓地」(『こもの文化財だより』第13号、1998年)
- 山川均『石塔造立』(法藏館、2015年)

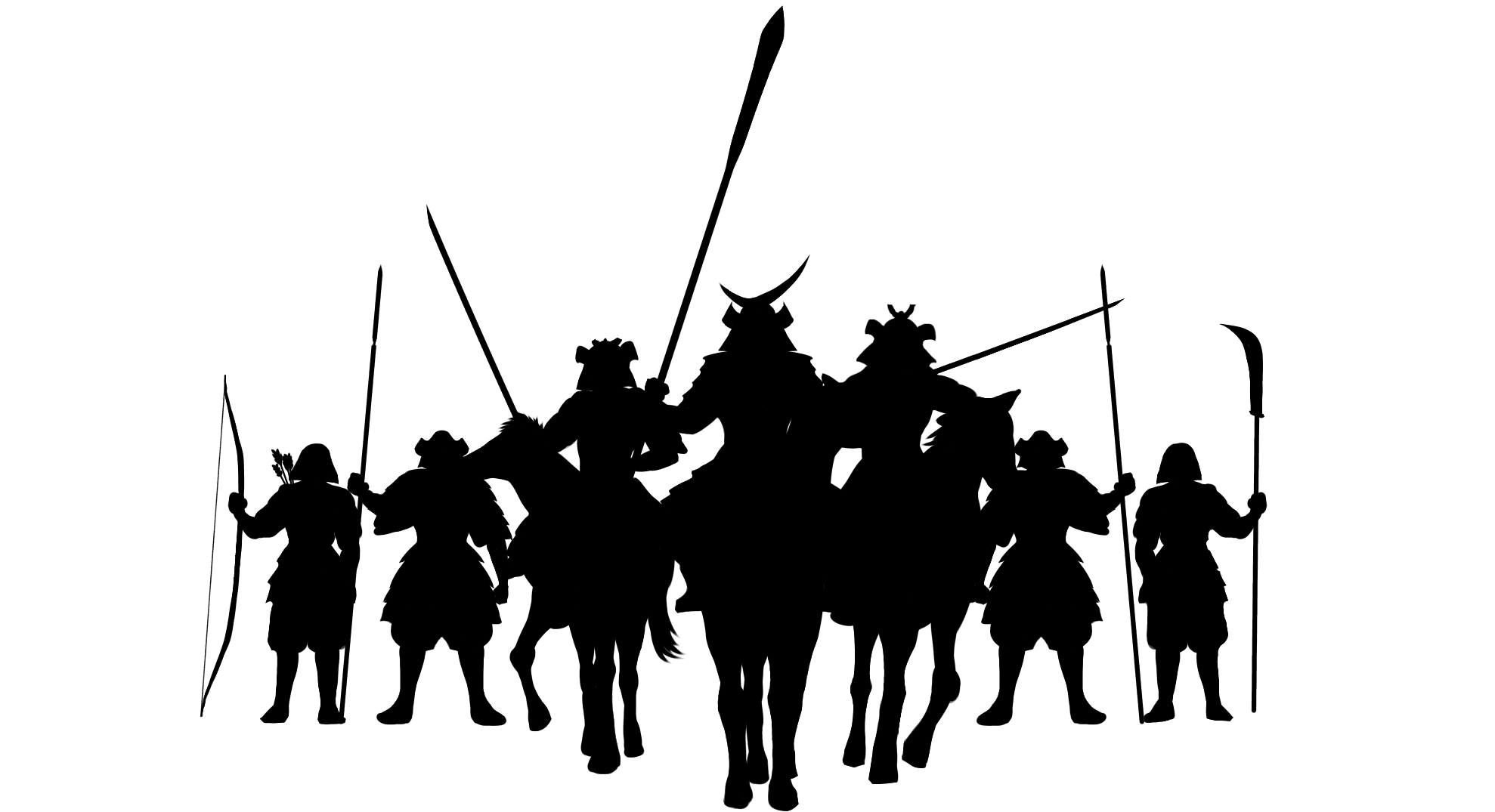

コメント