今回見ていくのは3国司の内、伊勢国の北畠氏と、土佐国の一条氏です。
北畠氏はゲームでは弱小大名とまではいかないかもしれませんが、南北朝時代から室町幕府と渡り合ったたくましい一族です。そんな一族も最後は織田信長に屈します。
一条氏は京都から遠く離れた土佐国で京都ともしっかりとつながりを持ち、地域支配を行った一族で、弱小なんてとんでもないです。ただ、最後が家の内紛?で衰退したので、後味が悪いのかもしれません。
教科書にも出てくる北畠氏
「北畠氏」と聞いて、皆さんは誰が思い付きますか?「誰も浮かばない」という人が一番多いんですかね、やはり。
北畠氏は高校の日本史の教科書であれば北畠親房が登場するぐらいでしょうか。南北朝の争いで南朝に味方し、「神皇正統記」を書いたことで有名?です。それと、日本地図に主な戦国大名が載った分布図で「北畠」とあると思います。いやいや、教科書に出てくるだけ前回の姉小路氏や次回の一条氏より好待遇ですね。
北畠氏の本拠地・伊勢国多気
ところで、先程の戦国大名の分布図で「北畠」とある場所はどこか?それは伊勢国(現在の三重県の一部)です。東の尾張には織田信長がいます。しかし、北畠氏の本拠は、織田家の尾張との国境からは離れた、伊勢国中部の多気(たげ。現在の三重県津市美杉町。)です。
多気は内陸部で、周囲を山に囲まれた地ですが、大和国と伊勢神宮を結ぶ伊勢本街道の途中にあり、交通の要衝でした。領地の支配には不便な場所のように思いますが、北畠氏は伊勢国内の支城に一族を配置することで、多気の地から各地の支配を行っていました。
北畠氏の伊勢入国と定着―伊勢国司家の始まり―
北畠氏は公家で、南北朝の争いが始まると、親房は信頼を得ていた後醍醐天皇の南朝に味方します。天皇が足利尊氏に敗れた頃、長男の顕家は東国におり、親房は再起を図って次男の顕信と共に伊勢国に入ります。伊勢国を選んだ理由はいくつか推定されていますが、不明なようです。
しかし、顕家はやがて戦死します。親房は態勢を立て直すべく、次男の顕信とともに東国へ赴きます。伊勢国には三男の顕能を残し、国司に任じます(当時の親房は伊勢国司を任命する権限を持っていたとされます)。これが伊勢国司としての北畠氏の始まりです。
南北朝合一と室町時代の北畠氏―恭順と反抗―
その後も、顕能は室町幕府との戦いを続けます。なお、顕能は最終的には従一位右大臣になっており、いかに厚遇されていたかがわかります。
顕能の没後、足利義満によって南北朝合一が果たされます。北畠氏は幕府に従い、幕府は、伊勢国司として北畠氏の伊勢国の一部支配を認めました。
その後、北畠氏は幕府に反抗して挙兵し、領地を没収されることもありましたが、やがて赦免されます。また、伊勢神宮の支配地域にも進出を図っています。
応仁・文明の乱を経て戦国時代を迎えても、北畠氏は周辺の勢力や伊勢神宮のある宇治・山田との争いを続けています。また、北畠氏の一族内部でも抗争が起きたことがありました。
織田信長の伊勢国侵攻―北畠氏の滅亡―
時代は進み、信長が桶狭間の戦いで今川義元を破った頃、北畠氏は具教(とものり)が家督を継承します。具教はやがて織田信長の伊勢侵攻を迎えます。
具教は信長と戦い、信長も苦戦しますが、信長の次男信雄(当時は具豊)を具房(具教の子)の養子とすることで和睦します。
信雄は北畠氏の家督を継承しますが、具教との確執もあったようで、ついに天正4(1576)年、具教と一族が謀殺されます。南北朝時代以来、幾多の争いの中で勢力を維持してきた北畠氏はここに滅亡します(厳密には、この後も具教の弟具親が再興を目指して挙兵する等の動きがあります)。
北畠氏は姉小路氏より少し早く国司として伊勢国に根付き、南北朝の争いや一族内部・周辺勢力との争いの中を戦国時代まで生き延びた一族です。伊勢国に入って間もなく国司となり、足利義満からも国司として認められているので、明確な国司であったと言えるのではないでしょうか。
ちなみに、北畠氏の本拠多気の地には現在、山の上に霧山城跡が残っています。その下には北畠神社が鎮座し、神社の庭園は室町時代のもので、北畠氏時代の遺構の一つとして残っています。
公家一条氏の土佐国入り
続いては一条氏です。その名字からイメージするのはやはり公家でしょうか。一条氏は五摂家(近衛・鷹司・一条・二条・九条)の一つで、鎌倉時代に九条家から分かれました。初代の一条実経が父の九条道家から分与された荘園の一つが土佐国幡多荘(土佐国西部)です。
時代は下り、室町時代に応仁・文明の乱が起きると、一条兼良は奈良へ疎開し、その子教房は関白も務めた人物で、応仁2(1468)年に土佐国幡多荘へ赴きました。これは幡多荘の支配強化のためと考えられています。
教房は幡多荘の中村を拠点とし、亡くなるまでの12年間で荘園支配の強化に努め、周辺地域の領主との結びつきも深めます。
土佐と京都の2方面作戦?―土佐での勢力拡大―
教房が亡くなった時、子の房家はまだ幼く、周辺の領主等に擁立されて跡を継ぎました。房家は成長の後、土佐で在地の支配に努めます。
一方で、一時上洛して次男を京都の本家の養子とする等、土佐国に居ながら京都との繋がりも維持していました。そのような中、房家は土佐国司となります。
房家の時代には、長宗我部兼序が敗戦により自害します。兼序は前もって子(後の国親。元親の父。)を土佐一条氏のもとへ脱出させ、房家が保護したという説もあります。
更に、孫の基房の頃(16世紀前半)に、土佐一条氏は土佐国の約半分を支配する大名と言える存在になったと考えられています。
また、土佐国の南を通る航路が使われた関係から、土佐一条氏は対外貿易に関与していた可能性も指摘されています。京都との関係や交易への関与(の可能性)など、幅広く活躍していたことがわかりますね。
長宗我部氏の台頭と一条兼定の隠居―再び京都本家一条氏の登場―
兼定の代には長宗我部家(元親)の勢力が拡大し、土佐一条氏の味方であった周辺領主が長宗我部氏に味方する動きを見せるなどします。
そのような中、天正元(1573)年に土佐一条氏の一部の家臣が兼定を隠居させて子内政を擁立し、長宗我部氏との和平を目指します。兼定は抗しきれず、天正2(1574)年2月に拠点の中村を出て、妻の父である大友宗麟のもとへ逃れます。内政は中村から別の城へ移されます。
ところで、この兼定の隠居については、天正元年に京都の本家一条家から当主内基が土佐へ来た直後の出来事です。本家当主の滞在中に、家臣が兼定を強制隠居させる事件を起こすか?という点で違う説も出されています。
家臣が隠居させて追放したというのは後世の軍記物に書かれた内容です。実際は本家の内基が土佐一条氏内部の問題解決のために土佐に来て、兼定を隠居させ、子の内政を当主として長宗我部元親に保護を依頼したのではないか?という説です。
兼定の復権作戦と挫折―一条氏の終焉―
内基は兼定が豊後へ向かった翌年(天正3年)5月に京都へ戻っています。この年、兼定は四国に戻って中村の奪回を目指します。しかし、8~9月頃とされる渡川の戦いで敗れ、10年後に戸島(宇和島の西方の島)で死去します。確かに、本家の内基が京都へ帰った直後に戦いが起きていることからも、兼定の隠居には内基の関与があり、兼定には不満があったのかもしれませんね。
以上のようにして、長宗我部氏の支配が徐々に拡大・浸透し、土佐一条氏の支配は実質的に終焉を迎えます。
土佐一条氏も姉小路氏や北畠氏と同じく公家であり、土佐国の一部の支配でしたが国司となっています。兼定の代まで国司であったのかは調べてもわかりませんでしたが、その支配は前述のようであり、京都との繋がりを考えても、決して軽視できるものではないと思います。
3国司は弱小ではない!
さて、2回に分けて3国司を見てきましたが、ゲームにあるような弱小大名のイメージとは異なりませんか?
「国司」は形骸化したものだったのかもしれませんが、その支配は決して軽く見ることはできないと思います。姉小路・北畠・一条氏のいずれも、京都との繋がりを持ち、一国ではないとはいえ、盤石な支配を行ったという意味では、「国司」の称号はあながち形だけのものではなかったのかもしれません。
《参考文献》
- 橋本政宣編『公家事典』(吉川弘文館、2010年)
- 朝倉慶景「天正時代初期の土佐一条氏(上)」(『土佐史談』166号、1984年)
- 朝倉慶景「天正時代初期の土佐一条家(中)」(『土佐史談』167号、1985年)
- 朝倉慶景「天正時代初期の土佐一条家(下)」(『土佐史談』172号、1986年)
- 朝倉慶景「天正時代初期の土佐一条家(下の二)」(『土佐史談』175号、1987年)
- 藤田達生編『伊勢国司北畠氏の研究』(吉川弘文館、2004年)
- 三重県埋蔵文化財センター『北畠氏とその時代』(2006年)
- 石野弥栄「戦国期南伊予の在地領主と土佐一条氏―戦国期の諸合戦の展開をめぐって―」(市村高男編『中世土佐の世界と一条氏』、吉川弘文館、2010年)
- 荻慎一郎・森公章・市村高男・下村公彦・田村安興『高知県の歴史』(第二版、山川出版社、2012年)
- 『三重県史』通史編中世(三重県、2020年)
- 『寺院に伝わる戦国の残像~北畠氏のいた時代~』(三重県総合博物館企画展図録、2021年)
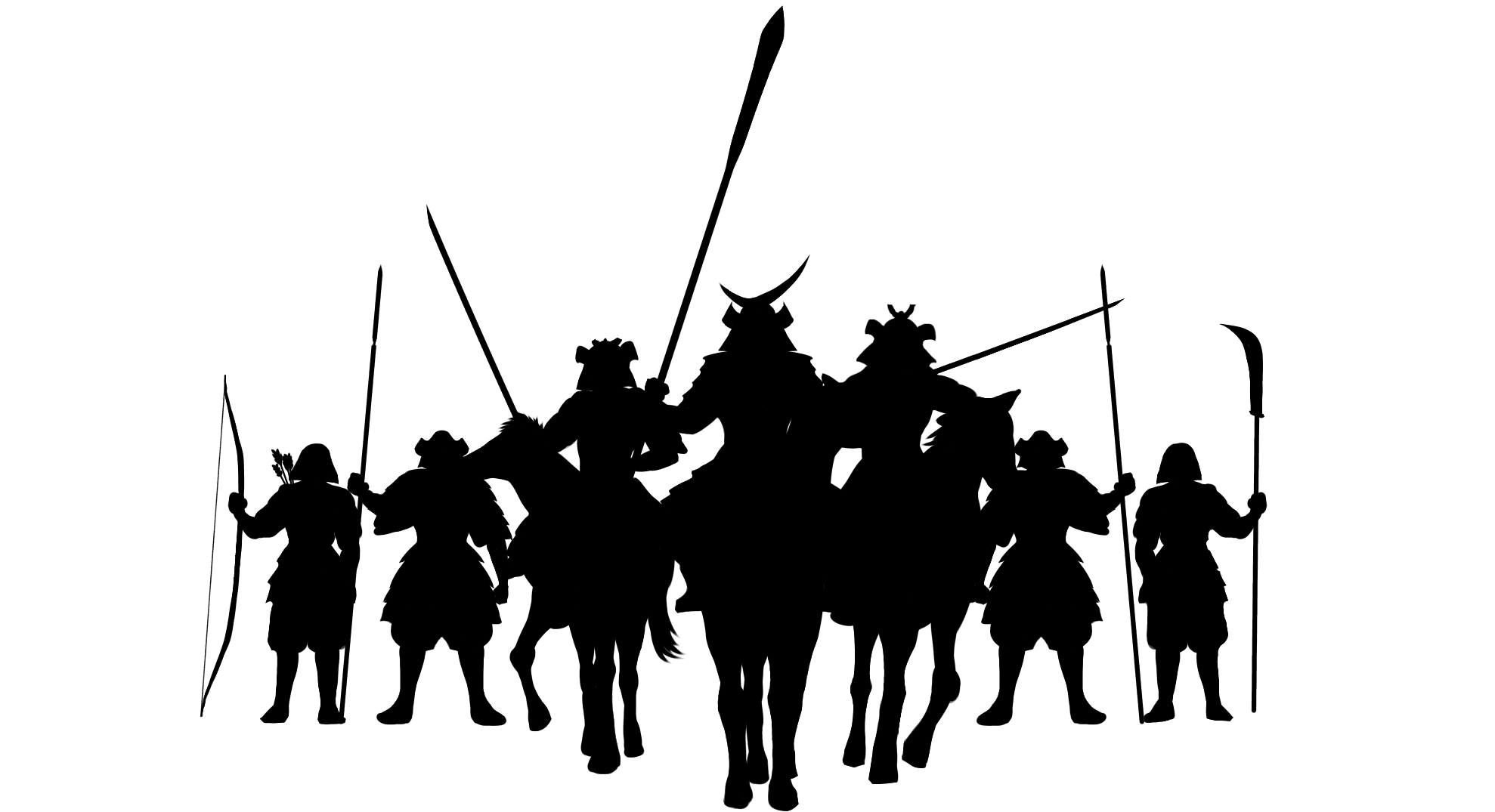
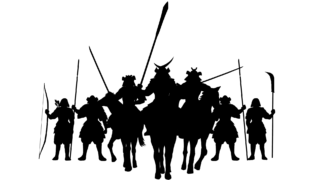

コメント