今回は奈良県橿原市にある古墳を紹介します。橿原市は奈良県中部にあり、場所が場所だけに、多数の古墳があります。
橿原市には有名な橿原神宮があり、初代天皇の神武天皇と皇后の媛蹈韛五十鈴媛皇后を祭神として祀っています。そして、その周辺には天皇陵とされる古墳が集まっています。今回は多数の古墳の中から、天皇陵を中心に紹介します。
※以下の各天皇の経歴等は『古事記』や『日本書紀』で伝えられているものであり、史実とは限りません。
橿原神宮
橿原神宮は近鉄橿原神宮前駅のすぐ近く(駅の北西)にあります。駅から橿原神宮の正面入口の鳥居までは徒歩10分足らずです。周辺の古墳を見て回るのであれば、駅の東口方面でレンタサイクルを借りると便利です。
橿原神宮は初代天皇の神武天皇と皇后の媛蹈韛五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと)を祭神として祀っています。




神武天皇は日向(現在の宮崎県)を出発して東へ向かい(神武天皇の東征)、紀伊(現在の和歌山県と三重県南部)東部に上陸して大和を目指します。やがて大和に入った後、橿原の地に館を設け、辛酉の年(紀元前660年)に初代天皇の位につきました。76年間在位し、127歳で崩御したとされています。
※神武天皇については下の記事もお読みください。
神武天皇陵
ここから天皇陵を順番に紹介していきますが、橿原神宮の北東(近鉄畝傍御陵前駅の西)にある橿原考古学研究所附属博物館に行くと、古墳等について予め学ぶことができます。
神武天皇陵は博物館の西にある道を北に進むとあります。
神武天皇陵は「畝傍山東北陵(うねびやまのうしとらのすみのみささぎ)」という名前です。形は円丘になっており、その周辺に四角形の周濠(古墳の周りをとりまく堀)があります。
東側の道路から長い参道を進んでいくと見えてきます。


確かに大きいですが、以前に紹介した日本最大の仁徳天皇陵(大仙古墳)に比べるとかなり小さく感じます。初代天皇ではありますが、古墳はそれほど大きくはありません(←大仙古墳が大きすぎるだけかも)
平安時代までは神武天皇陵がどの古墳かは定まっていたようですが、その後、どの古墳かが忘れられたようです。江戸時代には人によって、どれを神武天皇陵とするかが異なったようです。江戸幕府は、次に紹介する綏靖天皇陵を神武天皇陵と考えました。
幕末に奈良奉行の川路聖謨が現在の神武天皇陵が正しいとする説をとなえ、文久3(1863)年に朝廷により、ここが正式に神武天皇陵に決定されました。
綏靖天皇陵
綏靖(すいぜい)天皇は第2代の天皇です。神武天皇の子で、母は媛蹈韛五十鈴媛皇后です。名前を神渟名川耳尊(かんぬなかわみみのみこと)といいます。
神武天皇の崩御後、兄とともに異母兄を討って、翌年に即位しました。母の妹である五十鈴依媛命(いすずよりひめのみこと)を皇后としました(異説あり)。
即位して33年間在位し、84歳(45歳説もあり)で崩御しました。
綏靖天皇陵は神武天皇陵(の周りの森林)の北東に接しています。
神武天皇陵ほど長くはありませんが、東側の道路から参道が続いています。


綏靖天皇陵は「桃花鳥田丘上陵(つきだのおかのえのみささぎ)」という名前で、形は円丘です。
神武天皇陵と同様に鎌倉時代以降、どれが綏靖天皇陵かわからなくなっていました。江戸幕府によって現在の綏靖天皇陵が神武天皇陵とされたために、現在とは別の古墳が綏靖天皇陵だと考えられていました。前述のように、文久3年に神武天皇陵は現在の場所と定められましたが、綏靖天皇陵は現在とは別の古墳とされたままでした。現在の古墳が綏靖天皇陵と定められたのは明治11(1878)年です。
安寧天皇陵
安寧(あんねい)天皇は第3代の天皇です。綏靖天皇の子で、母は五十鈴依媛命です(異説あり)。名前を磯城津彦玉手看尊(しきつひこたまてみのみこと)といいます。
父の綏靖天皇の崩御にともなって即位しました。母方の又従兄弟の娘である渟名底仲媛命(ぬなそこなかつひめのみこと)を皇后としました。
即位して38年間在位し、57歳(49歳説もあり)で崩御しました。
安寧天皇陵は橿原神宮の西方にあります。
古墳の東側に入口があります。


北に少し離れると古墳全体を見ることができます。下の写真の森全てが安寧天皇陵です。

安寧天皇陵は「畝傍山西南御陰井上陵(うねびやまのひつじさるのみほどのいのえのみささぎ)」という名前です。形は東西に長い楕円形です。
安寧天皇陵も時代とともに、どの古墳なのかわからなくなっていましたが、元治元(1864)年には現在の古墳が安寧天皇陵として修復されています。
懿徳天皇陵
懿徳(いとく)天皇は第4代の天皇です。安寧天皇の子で、母は渟名底仲媛命です(異説あり)。名前を大日本彦耜友尊(おおやまとひこすきとものみこと)といいます。
父の安寧天皇の崩御にともなって、翌年に即位しました。皇后は安寧天皇の孫(懿徳天皇の姪)の天豊津媛命(あまとよつひめのみこと)です。
即位して34年間在位し、77歳(45歳説もあり)で崩御しました。跡は子の孝昭天皇が継ぎました。
懿徳天皇陵は安寧天皇陵のすぐ東南東にあります。
入口は古墳の南側です。


古墳の南西部には池がありますが、周濠の一部でしょうか。
-1024x768.jpg)
懿徳天皇陵は畝傍山南纖沙溪上陵(うねびやまのみなみのまなごのたにのえのみささぎ)という名前です。形は円丘です。
懿徳天皇陵も時代とともに、どの古墳なのかわからなくなっていましたが、安寧天皇陵と同様に元治元(1864)年に、現在の古墳が懿徳天皇陵として修復されています。
孝元天皇陵
孝元天皇は第8代の天皇で、孝霊天皇の子です。4代懿徳天皇から、5代孝昭天皇、6代孝安天皇、7代孝霊天皇と、代々子へと皇位が受け継がれ、8代孝元天皇に至ります。名前を大日本根子彦国牽尊(おおやまとねこひこくにくるのみこと)といいます。
父の孝霊天皇の崩御にともなって、翌年に即位しました。皇后は欝色雄命(うつしこおのみこと)です。
即位して57年間在位し、116歳(57歳説もあり)で崩御しました。跡は子の開化天皇が継ぎました。
孝元天皇陵は近鉄橿原神宮前駅の東方800mほどの所、石川池の南にあります。
入口は古墳の南側です。

孝元天皇陵は上の方まで登って行くことができ、登った先に参拝所があります。


南以外の三方は石川池に囲まれています。
-1024x768.jpg)
孝元天皇陵は劒池嶋上陵(つるぎのいけのしまのえのみささぎ)という名前で、通称は中山塚です。形は前方後円墳とされています。名前からすると、石川池が「劒池」で、そこの島にある陵ということになるのでしょうか。
孝元天皇陵も時代とともに、どの古墳なのかわからなくなっていましたが、江戸幕府によって現在の孝元天皇陵が定められました。
なお、孝元天皇の姉妹には倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)がいます。倭迹迹日百襲姫命は卑弥呼という説もあり、墓は古墳時代初期では最大級の規模の箸墓古墳(奈良県桜井市)とされています。
宣化天皇陵
宣化天皇は第28代の天皇で、継体天皇の子です。継体天皇は武烈天皇の次に即位しますが、かなり遠い親戚で、その即位には王朝交代説(武烈天皇までとは違う一族が天皇になったという説)もあります。詳細は以下の記事を参照してください。
宣化天皇は西暦467年に生まれ、名前を檜隈高田(ひのくまのたかだ)といいます。兄の安閑天皇の崩御にともなって536年に即位しました。皇后は第24代仁賢天皇(武烈天皇の父)の娘の橘仲(たちばなのなか)皇女です。
即位して3年後の539年に73歳で崩御しました。跡は弟の欽明天皇が継ぎました。
宣化天皇陵は近鉄橿原神宮前駅の西南西1.5kmほどの所にあります。
古墳の北側に参拝所があります。

北・西・南は周濠があり、東には池があります。
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
-1024x768.jpg)
すぐ手前の家と比べると、古墳の大きさがわかります。
宣化天皇陵は身狹桃花鳥坂上陵(むさのつきさかのえのみささぎ)という名前で、皇后とともに葬られているとされています。形は前方後円墳です。
宣化天皇陵も時代とともに、どの古墳なのかわからなくなっていましたが、江戸幕府によって現在の宣化天皇陵が定められました。
宣化天皇の在位中の538年は仏教伝来年の説の一つです。また、大伴金村・物部麁鹿火を大連、蘇我稲目を大臣としました。大伴金村は歌人として有名な大伴旅人・家持父子の先祖、物部麁鹿火は聖徳太子の頃に蘇我馬子とともに有名な物部守屋の一族(麁鹿火の曽祖父と守屋の曽祖父が兄弟)、蘇我稲目は馬子の父にあたります(馬子の子が蝦夷、蝦夷の子が入鹿)。
神武・綏靖・安寧・懿徳・孝元天皇は実在したか否かも歴史学的には証明されておらず、ありえない年齢の天皇もいますが、28代の宣化天皇になると、そうでもなくなってきますね。
桝山古墳
ここからは天皇陵ではない古墳を2つ紹介します。
一つ目は桝山古墳です。桝山古墳は宣化天皇陵の更に南200mほどの所にあります。
古墳の北東側に参拝所があります。

-1024x768.jpg)
少し離れて見ると、その大きさわかります。一緒に写っている車やビニールハウスがかなり小さく見えるほどです。
航空写真で見ると前方後円墳に見えますが、この形は幕末に修復された際に改変されたもので、元々は方墳です。方墳としては日本最大規模です。実際に見ると、確かに前方後円墳のように丸みを帯びた部分があります(下の写真)。
-1024x768.jpg)
この桝山古墳は第10代の崇神天皇の皇子である倭彦命(やまとひこのみこと)の身狭桃花鳥坂墓(むさのつきさかのはか)とされています。
宣化天皇陵は「身狹桃花鳥坂上陵」なので、「上」の文字があるか無いかだけの違いです。「上」が文字通りの意味であれば、「上」の付く宣化天皇陵が桝山古墳よりも上にあるように思いますが、実際は宣化天皇陵の方が桝山古墳よりも少し低い位置にあります。
崇神天皇は先ほどの第8代孝元天皇の子の第9代開化天皇の子(孝元天皇の孫)にあたります。崇神天皇を事実上の初代天皇とする説もあります。
崇神天皇の子には11代の垂仁天皇がおり、桝山古墳の主とされる倭彦命の兄弟にあたります。
丸山古墳
二つ目は丸山古墳です。孝元天皇陵の南東約700mの所にあります。
ここには参拝所は無く、墳丘の中腹(下の写真の中央部の白い看板のところ)まで登ることができます。

丸山古墳は奈良県内最大、全国でも6番目の大きさの前方後円墳です。下の写真の木の生えている所だけではなく、写真の右端から左端まで、全て丸山古墳です(右が前方部、左が後円部)。長さは約330mあります(東京タワーを横にしたのとほぼ同じ)。かつては周濠もありました(現在は窪地になっているが水は無い)。
-1024x768.jpg)
丸山古墳の石室(棺を安置する空間(玄室)とそこに至る通路(羨道))は全国でも最大規模の大きさです。玄室に至る羨道(せんどう)も非常に長いものです。
ここに葬られているのは、宣化天皇の次の第29代欽明天皇や蘇我稲目という説があります。
以上が橿原神宮周辺の古墳です。どの古墳もなかなか写真に収めることが難しいほどの大きさがあります(少し離れて見ると大きさがわかりやすいが、周辺の建物で全貌が見えない場合も多い)。
特に天皇陵は中に入れませんし、木が茂っているので、なかなか形がわかりにくいです。一方で丸山古墳は木が少なく、周囲に山や家が少ないので、上の写真のように全体がよくわかります。
橿原の地は神武天皇が最初に即位した地だからこそ?天皇陵が集まっています。これだけ近距離で多くの天皇陵を見ることができるのは珍しいのではないでしょうか。
なお、天皇陵は即位順に紹介したので、場所順は考慮していません。順番に回ろうと思えば、橿原神宮前駅→橿原神宮→橿原考古学研究所附属博物館→神武天皇陵→綏靖天皇陵→安寧天皇陵→懿徳天皇陵→宣化天皇陵→桝山古墳→丸山古墳→孝元天皇陵→橿原神宮前駅の順が一つのルートです。レンタサイクルで約2時間あれば回れます。ただし、坂道も多いので、電動自転車の方がよいかもしれません。
※記事の内容は2025年6月時点のものです。
《参考文献》
- 『日本史広辞典』(山川出版社、1997年)
- 米田雄介編『歴代天皇年号事典』(吉川弘文館、2003年)
- 宮内庁ホームページ(最終閲覧:令和7年6月19日)
- 橿原市観光協会ホームページ(最終閲覧:令和7年6月19日)
- 現地の案内板



-160x90.jpg)
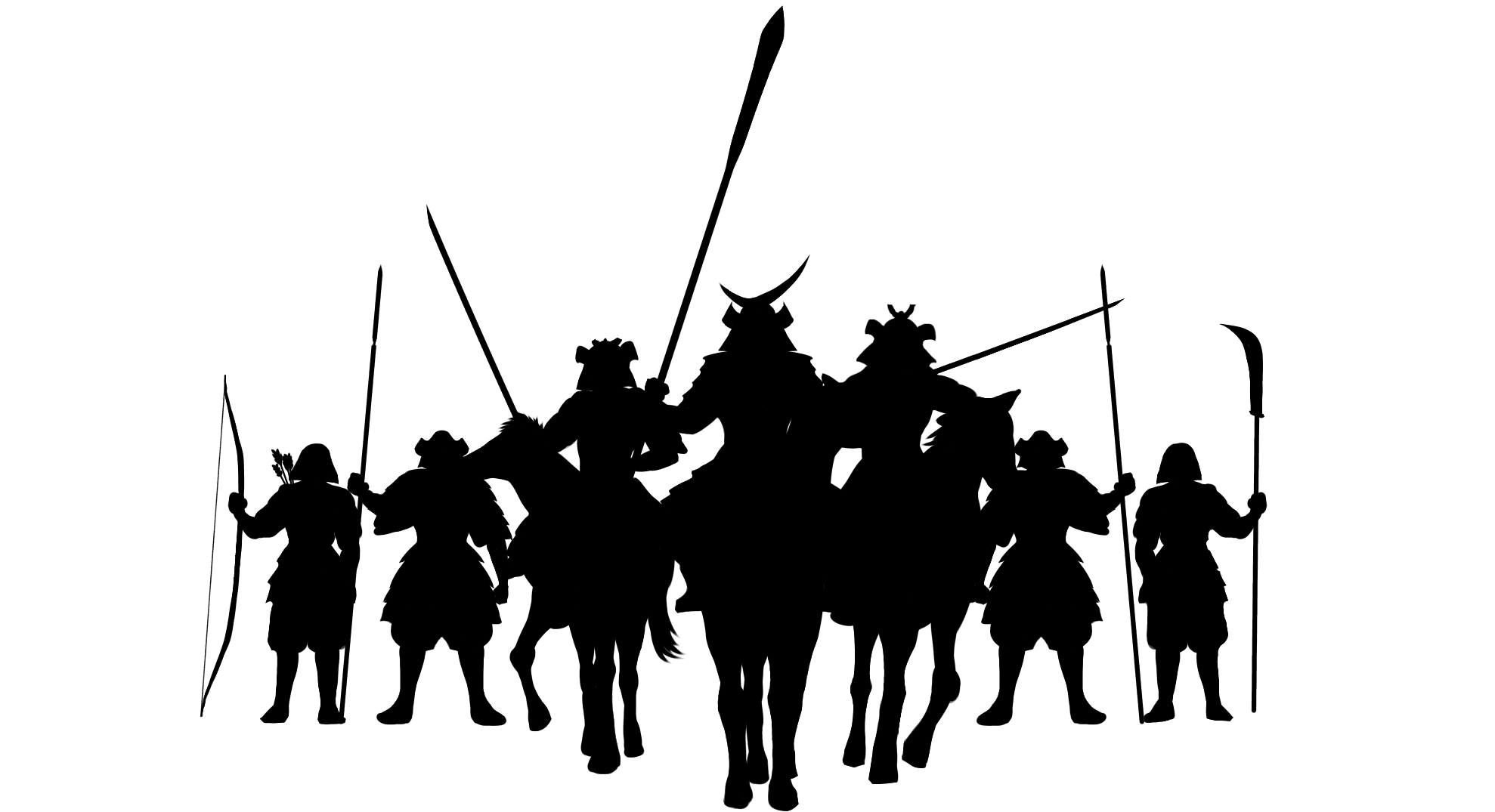
.jpg)
コメント