 史跡紹介
史跡紹介 大阪府堺市出身の人々ゆかりの地2~河口慧海~
大阪府堺市出身の人物として、前回は千利休・与謝野晶子のゆかりの地を見ました。今回は河口慧海です。河口慧海について河口慧海。千利休・与謝野晶子と比較して、その名を聞いたことがある人は少ないでしょう。しかし、とてつもない苦難を経て日本の仏教のた...
 史跡紹介
史跡紹介  日本史あれこれ
日本史あれこれ  日本史あれこれ
日本史あれこれ 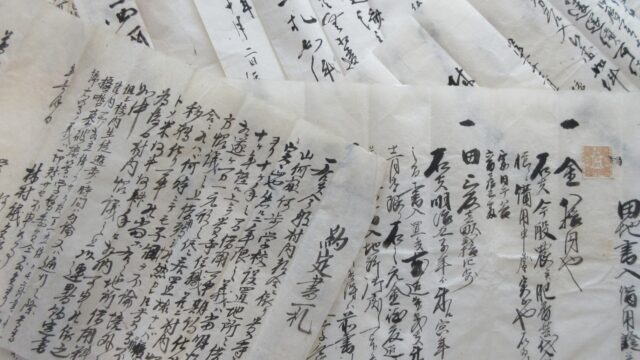 日本史あれこれ
日本史あれこれ  史跡紹介
史跡紹介  史跡紹介
史跡紹介  史跡紹介
史跡紹介 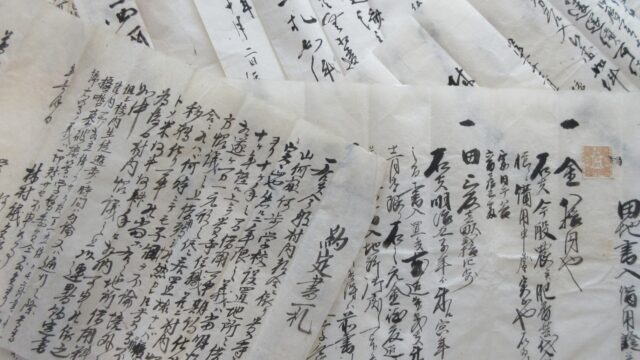 日本史あれこれ
日本史あれこれ 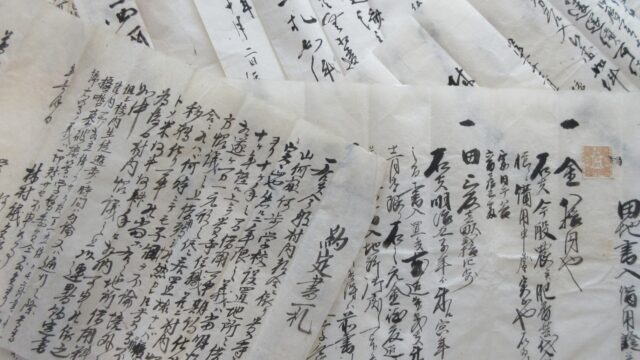 日本史あれこれ
日本史あれこれ 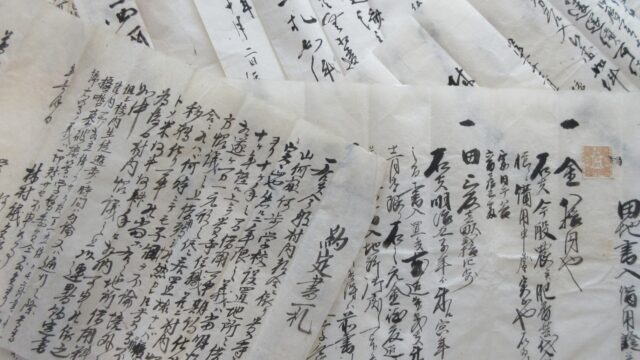 日本史あれこれ
日本史あれこれ