※令和7年10月21日、姉小路頼綱没後の姉小路(三木)氏の記述を追加しました。
戦国時代に国司?と聞くと変な感じがしますが、実は国司とされた(名乗った?)戦国大名がいました。今回は国司の概要と飛騨国国司の姉小路氏についてお話します(次回は北畠氏と一条氏です)。姉小路氏はゲームどおりの弱小大名かと思いきや、いやいや意外にすごいんです。ただ、最後は徐々に衰退したのか、別の一族が名跡を継ぎ(乗っ取り?)、本来の姉小路氏の末路は判然としません。
国司とは?―大岡や吉良も?―
国司(こくし)といえば何時代を連想しますか?奈良時代?平安時代?江戸時代はさすがに無いでしょうか。国司は朝廷(中央政府)から地方へ派遣され、その国(武蔵国、越前国、薩摩国など)の政治を行った役人です。
その国の長官は「~~守(かみ)」、次は「~~介(すけ)」というようにランクが分かれていました。例えば、大岡越前守忠相や吉良上野介義央はよく時代劇で聞きますよね。
「越前守」が国司の職名で、越前国(今の福井県の一部)の長官(現在の都道府県知事のようなもの)です。「上野介」は上野国(今の群馬県)の次官(現在の副知事でしょうか)です。
大岡や吉良の頃は江戸時代なので、既に名前だけの職になっており、大岡忠相も吉良義央も、もちろん越前国・上野国に行って統治したわけではありません。まぁ、名前だけといえども残っているなら、厳密には江戸時代も国司がいたことになりますが。
国司の始まり
さて、後の時代につながる国司の制度ができたのは奈良時代の少し前頃と言われています。制度ができた当初は、もちろんその国に行って政治を行いましたが、平安時代になると、だんだん制度が緩んできます。私利私欲に走る者、実際にその国には行かない者などが出てきました。有名な「尾張国郡司百姓等解」で地元の人々から訴えられた国司(藤原元命)もいました。
鎌倉時代以降の武士の時代になると、「国司」という言葉はいつの間にか教科書でも見なくなり(国や地方を治めるのは守護・地頭のイメージ?)、国司は自然消滅していったイメージではないでしょうか?
戦国時代の3国司
しかし、武士の時代にも国司を名乗り、その地を長く治めた一族がありました。時は戦国時代、場所は飛騨国(今の岐阜県の一部)・伊勢国(三重県の一部)・土佐国(高知県)です。
その国全域を治めたわけではなく、正式な国司か否かの問題はあるのですが、実際に国を治める国司が他にはいない時代に、実際に国司を名乗って、その国で支配を行ったという意味では珍しい存在です。
3国司と言われるのは諸説ありますが、今回は飛騨の姉小路氏、伊勢の北畠氏、土佐の一条氏とします。姉小路・北畠・一条という名字はいかにも「公家」「貴族」ってイメージじゃないですか?
ゲームでは弱小?
戦国ゲームの「信長の野望」で遊んだことがある人は、姉小路頼綱・北畠具教・一条兼定といった人物を聞いたことはないでしょうか?
姉小路氏・一条氏は弱小大名・武将であることが多く、北畠氏は少し良い方でしょうか。私がプレイしたシリーズでは姉小路氏が1ターンも回って来ずに攻め滅ぼされていることもありました(地元の方・ファンの方、ごめんなさい!でも、姉小路氏で全国統一もしましたよ)。
3氏とも江戸時代までは続きませんでしたが、武士の全盛期にもこの3国司がいたのです。今回と次回で、そんな戦国の3国司を順番に見ていきます。本当に弱小なのでしょうか?
公家の姉小路氏
3国司の順番にこだわりは無いので、北からいきます。最初は飛騨国の姉小路氏です。姉小路・北畠・一条の中では最も公家っぽい名字でしょうか。他にも公家では万里小路(までのこうじ)・勘解由小路(かでのこうじ)といった「●●小路」という家は多くあります。その由来は邸宅地のあった場所にちなんで名乗った等のようです。公家にも姉小路氏はいますが、飛騨の姉小路氏との関係はわかりませんでした。
飛騨の姉小路氏の登場
姉小路氏は南北朝時代の14世紀後半に飛騨国司となった公家の藤原家綱の家系と推定されています。しかし、家綱以外は正式に飛騨国司になった記録は無いようで、通称・自称と考えられています(そういう意味では厳密な国司ではないかもしれません)。
その後は3家(古川・小島・向)が分家します。本家は在京し、やがて活動が見られなくなります。3家は、一時期は京都で公家として活動した家もあれば、飛騨国を中心に活動した家もありました。
三木氏による姉小路氏乗っ取り?
戦国時代の1500年代に入ると、飛騨国内では地元の三木氏という勢力が力を伸ばしていきます。天文15(1546)年には三木直頼が「国主」を自称します。その子良頼は姉小路3家の一つである古川氏の名跡を継ぐべく朝廷に働きかけ、永禄2(1559)年に「三国司」の称号を得ます。ゲームに登場する姉小路氏はこの三木良頼や子の頼綱です。
翌年には飛騨国司に任ぜられ、正式に古川家を継ぎます。良頼はその後も従来の姉小路氏よりも高い官位を望むなど、従来の姉小路氏に対抗しようとしたと考えられています。
良頼が古川氏を継いだ時点で、もはや元々の古川氏の力は無くなっていたと推定されています。残る2つの分家については、向氏も活動が見えなくなっていきます。小島氏は本能寺の変が起きた天正10(1582)年には三木氏のもとで活動していたとされます。
つまり、姉小路氏の内の一つである古川家を継いだとはいえ、三木氏は本来の姉小路氏とは別の家ですので、この頃に従来の姉小路氏は衰退し、やがて絶えたのかもしれません。
ゲームとは正反対の姉小路氏(三木氏)―活躍と滅亡―
それにしても、ゲームでは弱小大名の姉小路氏(三木氏)ですが、飛騨国で勢力を拡大したり、朝廷工作を盛んに行ったりという姿を見ると、とても優れた政治力・軍事力を持っていると思いませんか?
その後、三木氏は上杉・武田・織田といった名だたる大名の間で勢力を維持し、この間に当主は良頼から頼綱、次いで秀綱に代わります。しかし、羽柴秀吉が金森長近に飛騨侵攻を命じ、三木氏は敗れます。
頼綱は京都に移った後、天正15(1587)年に亡くなります。子の秀綱は慶長5(1600)年9月に郡上城の戦いで戦死しました。別の子の近綱が家系を繋ぎます。
江戸幕府が編纂した大名・旗本の系図である『寛政重修諸家譜』によれば、近綱は遠藤慶隆のもとに身を寄せ、慶長19年の大坂冬の陣の時に徳川秀忠に仕えます。大坂夏の陣で戦功を挙げ、加増されて500石となります。
以降、子孫も幕府に仕え、少なくとも寛政期まで家系は続いています。
確かに姉小路氏は歴史の表舞台からは消えてしまいました。しかし、飛騨国で勢力を伸ばし、分家を作り、在京もした、決して弱々しい存在ではありません。
三木氏が姉小路氏を継ぐ形をとったのも、飛騨国で勢力を拡大するにあたり、姉小路氏を継ぐことが(正当性という意味で)有利だったからではないでしょうか?戦国時代の飛騨国において、それだけ姉小路氏は無視できない、大きな存在だったのです。
三木頼綱が秀吉に逆らっていなければ、もしかしたら江戸時代まで大名姉小路氏が存続していたかもしれませんね。
《参考文献》
- 阿部猛・西村圭子編『戦国人名事典コンパクト版』(新人物往来社、1990年)
- 『日本史広辞典』(山川出版社、1997年)
- 橋本政宣編『公家事典』(吉川弘文館、2010年)
- 『姉小路氏城館跡』(飛騨市教育委員会、2022年)
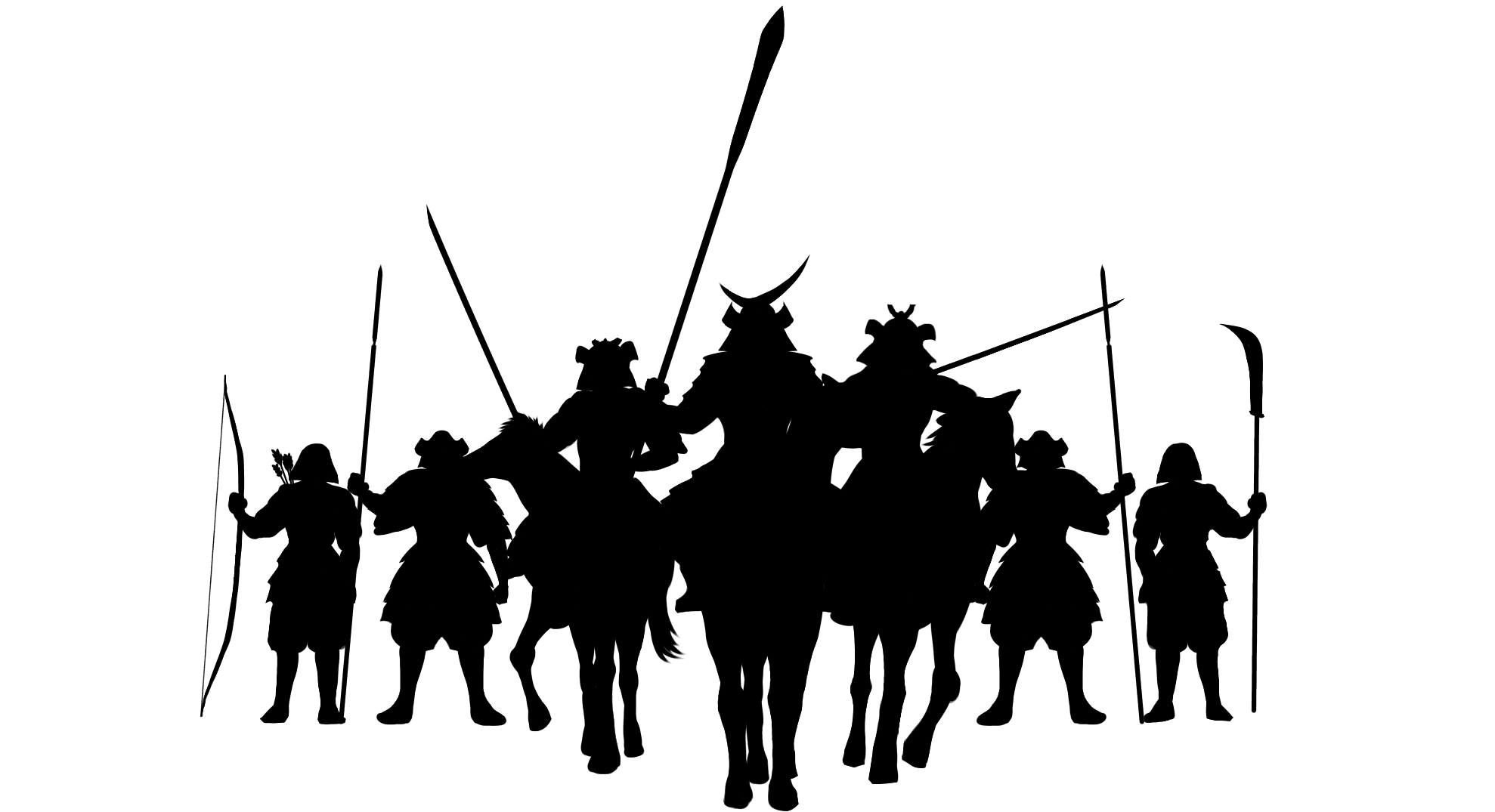
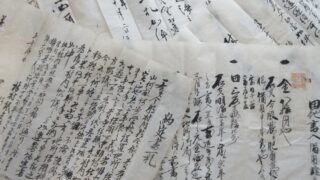
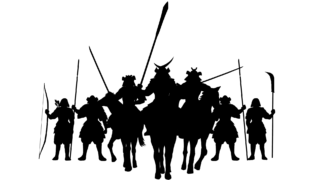

コメント