日本の旧国名には難しい読み方のものがあります。なかでも最難関なのが上野・下野ではないでしょうか。どう考えても、漢字と読み方が一致していません。それは、実は消えた文字があったからです。今回は、なぜこのような読み方になったのかを解説します。
読めない旧国名
日本には江戸時代まで(実際には明治時代も少しあると思いますが)使われていた旧国名があります。有名なところでは信濃(今の長野県)や伊勢(今の三重県の一部)、薩摩(今の鹿児島県の一部)などでしょうか。
この中には読み方が難しい国名もあります。例えば陸奥(むつ)や下総(しもうさ)があります。中でも初見では読めない(下総とかも難しいですが)のが上野と下野ではないでしょうか?いや、上野は吉良上野介が有名なので意外に読めるのかもしれません…。
上野は今の群馬県、下野は今の栃木県にあたります。
このブログを読んでいる方は歴史好きが多いと思うので、読める方が多そうですが、上野は「こうずけ」、下野は「しもつけ」と読みます。「上」を「こう」、「下」を「しも」と読むのはわかりますが、「野」と「ずけ」・「つけ」は結びつきませんよね。
元々は上野・下野ではなかった
なぜこうなったのか。実は、上野・下野は元々「上毛野」・「下毛野」でした。
元々、今の群馬県全域・栃木県南部の地域は毛野(けの・けぬ)という1つのまとまりになっていました。これが2つに分かれて「上毛野」・「下毛野」になりました。「国造本紀」という史料に、仁徳天皇の時期(古墳時代)に2つに分かれたと書かれているようですが、確証は無さそうです。
「上毛野」は「かみつけの・かみつけぬ」、「下毛野」は「しもつけの・しもつけぬ」と読みます。「つ」は「~の」というような意味になるでしょうか。「上の毛野」のような感じです。
ちなみに、上・下は当時の都に近い方が上、遠い方が下になっています。前や後も同じで、例えば越前(今の福井県の一部)・越中(今の富山県)・越後(今の新潟県)があります。
文字が抜ける
ここで途中の経緯はわかりませんが、国名の「毛」の字が抜けて、「上野」・「下野」になりました。ところが、読み方の方では「野(の・ぬ)」が抜けてしまったのです。
国名が2文字になったのは、和銅6(713)年に国名を2文字とするように定められたたためです。
上毛野 → 上野
かみつけの → かみつけ →こうずけ
(恐らく訛って読みが変化したのでしょう。「ず」も元は「づ」だったと想像します)
下毛野 → 下野
しもつけの → しもつけ
という感じです。これが難読国名になった経緯です(なぜ漢字と読み方で別の字が抜けたのかはわかりません)。
今も残る毛野の痕跡
「毛野」は上野・下野になるにつれて名前としては消滅したように思いますが、実際は現在もその痕跡があります。
例えば、この地域を指して「両毛」という呼び方があります。上毛野・下毛野で2つの毛野地域というような意味でしょうか。JRでも両毛線がありますし、東武鉄道の特急「りょうもう」も恐らく両毛が由来でしょう。
はるか古代に正式な国名ではなくなりましたが、「毛野」は現在もこの地域で生きているのです。
《参考文献》
- 『角川日本地名大辞典10 群馬県』(角川書店、1988年)
- 『日本史広辞典』(山川出版社、1997年)


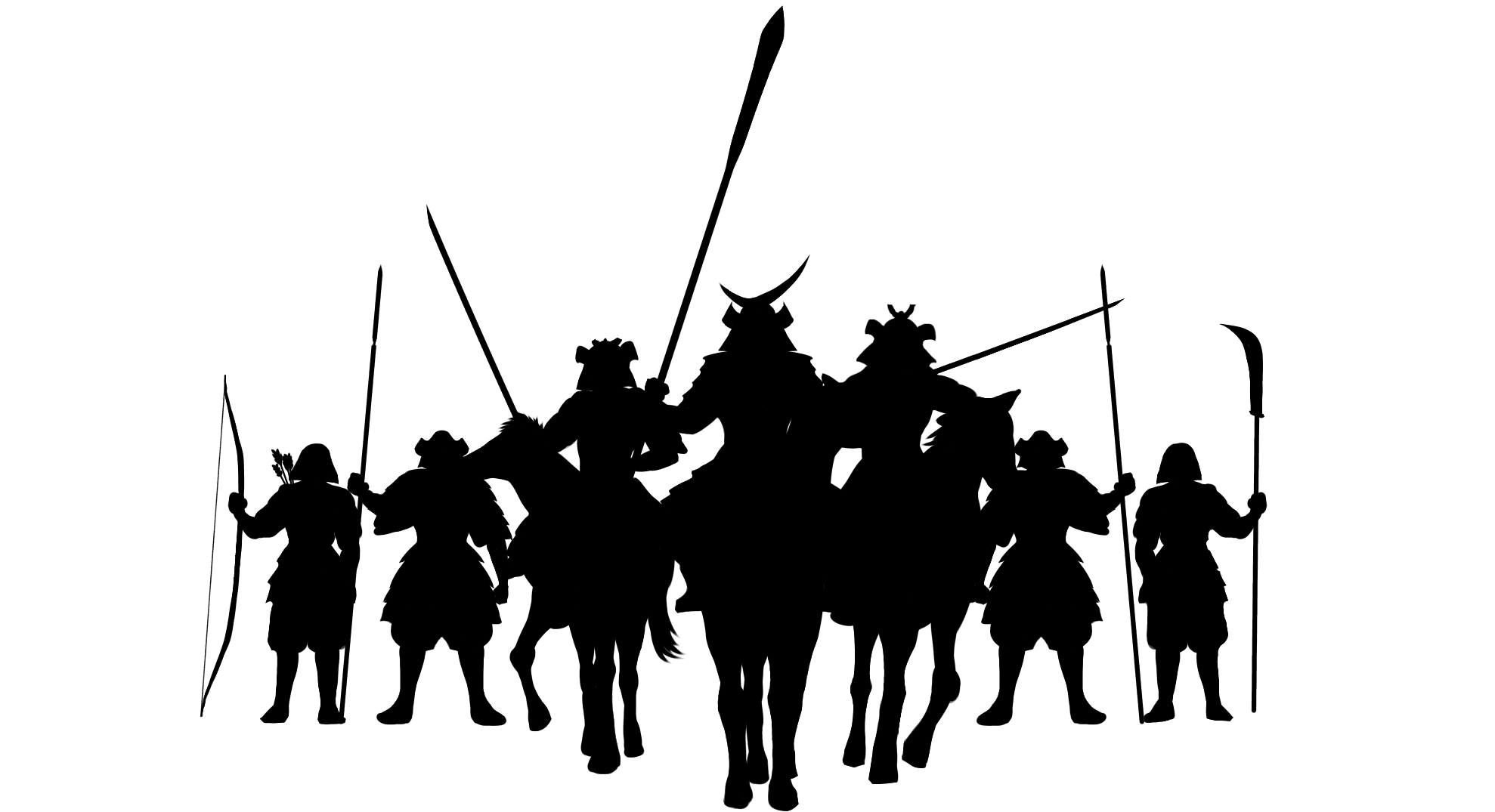
コメント