2023年の大河ドラマ「どうする家康」でも登場した石川数正。石川数正のイメージの一つに、突然徳川家康のもとから豊臣秀吉のもとへ出奔した(寝返った)ことがあるでしょう。家康の重臣だった数正は、なぜ突然このような行動に出たのでしょうか。最近の研究からその理由や背景を見ていきましょう。
石川数正の略歴
石川数正は言わずと知れた徳川家康の家臣です。生年は不詳ですが、幼少期は駿府で家康と共に過ごしました。家康にとっては人質時代から一緒にいる心強い家臣だったことでしょう。
永禄12(1569)年1月までに伯耆守と名乗っています。そして叔父の石川家成に代わって西三河の領主たちに対する指南(家康の意向を取り次ぎ、指示を行う役目)を務めました。
また、酒井忠次や石川家成と共に上杉氏との外交、徳川氏領国の内政にも宿老として携わりました。天正7(1579)年以降は岡崎城代を任されています。
天正10年6月、本能寺の変が起こった後、小笠原貞慶という武将が小笠原氏の旧領であった信濃国深志地域の奪還を試みます(小笠原氏は貞慶の父・長時の代に武田信玄に敗れて落ちのびていた)。この時、数正が取成しをして、貞慶は家康の援助を得ます。このことで貞慶との関係が生まれますが、その関係が後の数正の出奔に影響します。
ところで、数正は「数正」の名で有名ですが、実は天正13(1585)年3月までには家康から名前の1字を与えられ、「康輝」と改名しています。ただ、やはり「数正」が有名なので、以下でも表記は「数正」で統一します。
本能寺の変後、信長の後継者としての地位を築いていくのは羽柴(豊臣)秀吉です。家康と秀吉と言えば、本能寺の変後は良好とは言えない関係で、天正12年には小牧・長久手の戦いで軍事衝突します。この戦いは秀吉 対 織田信雄(信長次男)・徳川家康の構図ですが、信雄が秀吉と単独講和し、信雄の支援の名目で参戦していた家康も矛を収めます。
しかし、これで家康が秀吉に従ったわけではなく、以後も両者の駆け引きが続きます。数正は秀吉との外交交渉を担当する中で、融和外交に努めます。
そのような中、天正13年11月13日に突然、数正は家族と小笠原貞慶の子(人質として預かっていた)を連れて家康のもとを出奔し、秀吉のもとへ赴きます。
その後は秀吉に仕え、出雲守と名乗ります。名前も、秀吉から1字を与えられて吉輝に改めます。
天正18年、秀吉の小田原攻めで後北条氏が滅びた後、秀吉の命で家康は関東に移されます。数正は徳川氏が去った後の信濃国松本城主となり、8万石を領しました。
文禄元(1592)年には子の三長に家督を譲って隠居し、翌2年に亡くなりました。
なぜ出奔したのか?
さて、ここからが本題です。石川数正はなぜ家康のもとから出奔したのでしょうか。その理由は、徳川家内部で数正の方針(秀吉との融和方針)が採用されず、外交方針をめぐる争いに敗れたためという説があります。
従来は、家康は天正12(1584)年の小牧・長久手の戦いの終結以降も秀吉との対決姿勢を維持し、融和の考えは無かったかのように言われていました。
しかし、実は家康は少なくとも天正13年10月15日頃までは秀吉との融和を模索し、数正を秀吉のもとへ派遣するなどしていることが古文書からわかっています。家康は秀吉へ人質を送る方針(融和方針)でしたが、10月28日に突如方針転換し、人質は出さず、秀吉と決別することを決めてしまいます。数正が出奔したのはそれから約半月後の11月13日です。
数正出奔の原因と考えられている、この急な家康の方針転換の理由は何だったのでしょうか?なぜ数正の方針は採用されなかったのでしょうか?
そこには、先ほど書いた小笠原貞慶の動きがあったという説があります。
出奔の背景~数正と小笠原貞慶の関係~
先ほど書いたように、天正10(1582)年に本能寺の変が起こった後、小笠原貞慶は小笠原氏の旧領奪還を試みます。この時、数正が取成しをして、貞慶は家康の援助を得ます。結果として貞慶は旧領奪還に成功しました。
その後、貞慶は一時後北条氏に属したこともありましたが、徳川氏が信濃国を領有すると徳川氏に従います。そして数正は貞慶に家康の意向を取り次ぎ、指示を行う指南を務めます。
しかし、天正13年になると貞慶は密かに秀吉に通じます。このことは、秀吉が真田昌幸に宛てた同年10月17日付の書状(手紙)に書かれています。
書状の中で秀吉は昌幸に対し、貞慶と色々相談して行動するように命じています。秀吉に従っている真田昌幸と相談して行動するという事から、家康に従っていたはずの貞慶も秀吉に味方しているということがわかるのです。
少なくともこの書状が書かれた10月17日時点で、貞慶は秀吉に通じていました。一方の家康はこの貞慶の動きを知らなかったとみられています。
小牧・長久手の戦いで家康と共に秀吉と戦った織田信雄(信長次男)は、戦いの後に秀吉に従っていました。秀吉が真田昌幸に書状を送ったのと同じ天正13年の10月14日付で、信雄が家康に送った書状には、「(家康が)石川数正を(秀吉のもとに)派遣して、(秀吉と)相談するのは良い事でしょう」と書かれています。
家康が貞慶の裏切りを知っていれば、「秀吉は自分(家康)との交渉を進めておきながら、自分の味方である貞慶を寝返らせた(家康への背信行為)」と考えたでしょう。そうすれば秀吉との融和政策に影響したとみられます。しかし、この書状が書かれた10月14日頃の時点で、家康は秀吉と交渉しようとしており(別の史料からもそのことがわかります)、まだ貞慶の裏切りを知らなかったと考えられています。
恐らく家康は10月下旬になって貞慶の裏切りを知り、前述のように10月28日に秀吉へ人質を送る方針(融和方針)を撤回し、秀吉と決別することを決めます。
家康だけではなく、家康の家臣たちも人質を出さないことに同意していました。数正の方針は家康だけではなく、家康の家臣たちにも受け入れられなかったのです。
家康のもとで貞慶への指南(取次)を務めていた数正にすれば、貞慶が密かに家康を裏切って秀吉に味方したことは、自らの責任問題となります。当時、徳川家と外部(この場合は小笠原貞慶)の間で取次を務めることは、徳川家内部での政策決定への発言力が増すことにつながったとされています。
逆に、取り次いだ相手(貞慶)が裏切ったことにより、数正の責任問題となり、秀吉との融和政策を進める数正の発言力・信頼度が低下したと考えられます。このことにより、外交方針をめぐる争いに敗れたのです。
ともすれば、秀吉との交渉に派遣され、貞慶の指南であった数正自身にも内通の疑いがかかっていても不思議ではありません。
このようにして貞慶の裏切りに端を発し、徳川家の内部で責任問題となって発言力も失った(更に自身の身も危うかったかもしれない)数正は、秀吉のもとへ行くことになったのです。出奔の際、数正は貞慶から預かっていた人質(貞慶の子・後の秀政)を一緒に連れて行っており、やはり貞慶の行動が背景にあったと考えられています。
歴史は繰り返す?
さて、ここまで家康の重臣・石川数正が出奔するに至った理由・背景を見てきましたが、どうでしたか?流れをまとめると、
家康の秀吉との融和方針のもとで数正は活躍。小笠原貞慶への指南も務めた。
↓
貞慶が密かに家康を裏切って秀吉に味方。
↓
貞慶の裏切りを知った家康は秀吉との融和方針をやめ、決別を選択。家康の家臣も決別を支持。
↓
貞慶の指南であった数正の責任問題が浮上。それに伴って徳川家内部での数正の発言力が低下。秀吉との外交方針をめぐって融和派の数正は敗れる。
↓
自身の身も危うくなったかもしれない数正は家康のもとから出奔。
という流れです。数正は単に家康と秀吉を天秤にかけて有力そうな秀吉を選択したのではなく、徳川家内部での立場を失った末の出奔だったのです。数正としても出奔は進退窮まった末の選択で、本意ではなかったのかもしれません(←私の感想です)。
指南を務めた小笠原氏が裏切ったのは数正の責任も問われる事件だったでしょう。数正に責任が無いとは言えませんが、貞慶の裏切り、数正が秀吉との融和派であった(逆に徳川家は最終的に秀吉と決別した)ことなど、不幸な出来事が重なり、数正は長く仕えた家康のもとを去ることになったのです。
時代は少し戻り、本能寺の変は、織田信長の対四国政策をめぐる方針転換が原因の一つという説があります。長宗我部氏と信長の間を取り持っていた明智光秀。対して長宗我部氏と敵対する三好氏と関係があった羽柴秀吉。
信長がそれまでの長宗我部氏との友好政策から一転、敵対政策に転じたことで明智光秀が織田家内部での立場を失い、長宗我部氏を救うためにも本能寺の変に至ったというのです。
本能寺の変のような劇的な展開ではなかったものの、取次相手と主君との関係悪化によって立場を失ったという意味では、長宗我部氏(取次相手)・明智光秀と小笠原貞慶(取次相手)・石川数正は同じような気がします。
歴史は繰り返す、ということなのでしょうか・・・。
《参考文献》
- 『戦国人名辞典』(吉川弘文館、2006年)
- 柴裕之「石川康輝(数正)出奔の政治背景」(柴裕之『戦国・織豊期大名徳川氏の領国支配』、岩田書院、2014年)
- 菅原義勝「新出の織田信雄書状にみる石川数正出奔」(『日本歴史』第917号、2024年)
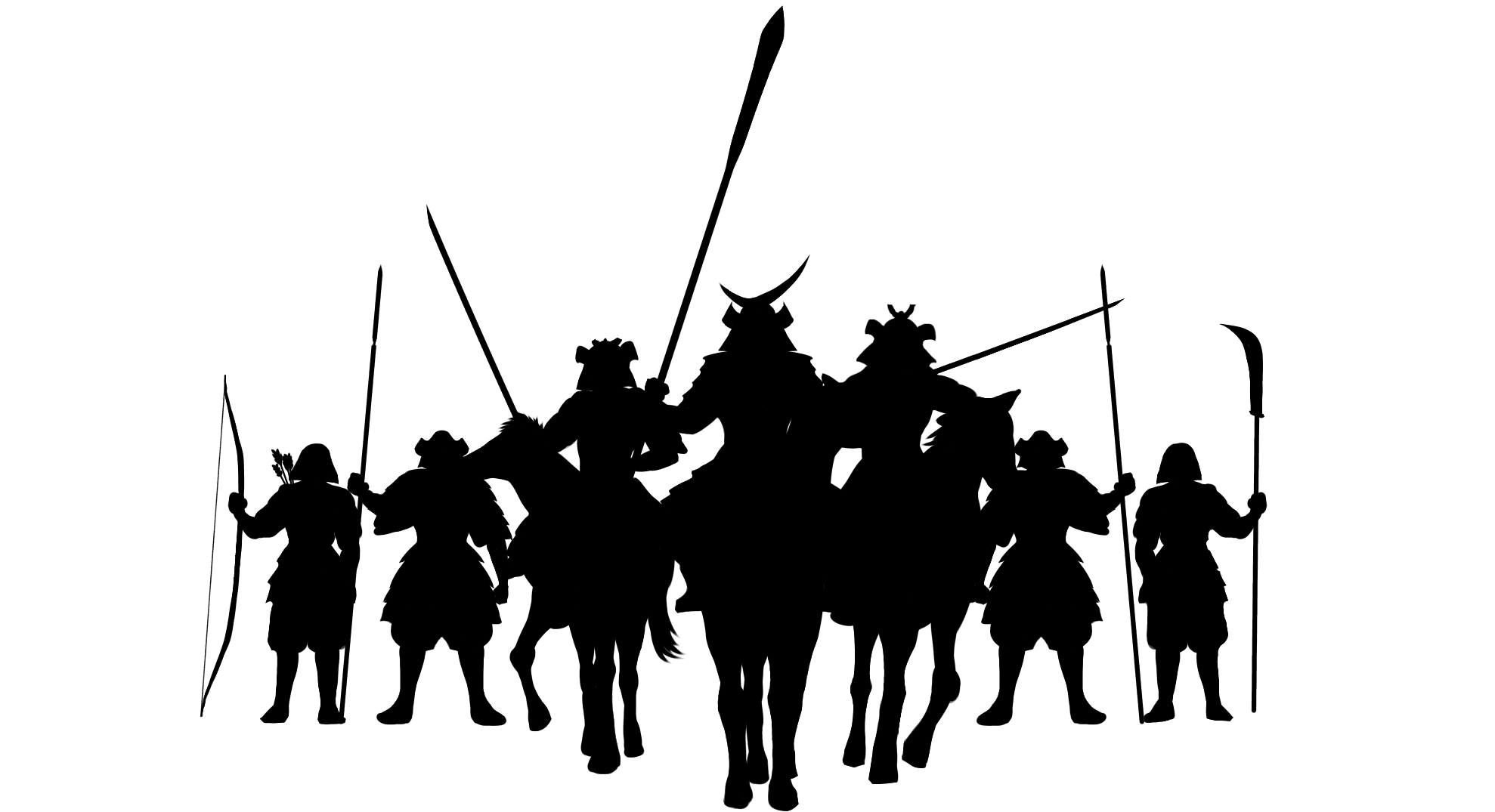


コメント