以前に少し藤堂高虎の話をしましたが、今回は現代の高虎の悪い評判について考えてみたいと思います。長くなるので、2回かに分けて書いていきますが、結論を言うと、別に悪くはないと思います。
1回目は高虎が仕えた1~5人目の主君について見ていきます。何度も主君を転々とし、運命の主君・豊臣秀長に出会います。
※前に少し書いた高虎の話はこちらです。
戦国時代の転職は悪いのか?
高虎はよく主君を7回変えた(8人の主君に仕えた)として、世渡り上手や風見鶏と言われ、この点では評価が良くありません。確かに、転職の多い人を会社で採用したいか?と言われると、ためらうことも多いでしょう。いつまた転職されるかわかりません。
しかし、少し立ち止まってみましょう。それは現代の考え方ではないですか?たしかに、戦国時代にも転職を良しとしない考えもあったでしょう。裏切り者と非難もされたでしょうが、生き延びるための裏切りならどうでしょうか。
現在でも、倒産寸前の会社と運命を共にする人ばかりではないと思います。最後まで尽くすのを良しとする考えもありますし、自分や家族の暮らしが大事とする考えもあるはずです。どちらの考えもアリではないですか?
戦国時代の転職は珍しくない―あの有名人も―
それに、戦国時代に転職は珍しくありません。高虎の家臣渡辺勘兵衛もその一人です。
他にも、秀吉は松下家に仕えた後に織田信長に仕えます。秀吉の軍師竹中重治(半兵衛)も最初は斎藤家家臣です。加賀百万石の前田家も信長→秀吉→家康です。
明智光秀は、不確実な面もありますが、最初は朝倉氏にいたとも言われ、その後、足利義昭、次いで信長です。
武田家滅亡後の真田昌幸は有名でしょう。昌幸も何回も主君を変えていますが、それも生き延びるためです。一方的に非難されるような生き方ではないでしょう。
新社会人?の高虎
では、高虎の退職・転職理由は何だったのでしょうか?ここから、主に『高山公実録』から見ていきたいと思います。
『高山公実録』は江戸時代の終わり頃に津藩(藤堂家)で作られた高虎の伝記です。様々な史料を集めて真実が何なのかを研究して書かれています。但し、誤りもあります。「高山(こうざん)」は高虎のことで、高虎の戒名(死後に付けられる名前)の一部から来ています。
高虎は、最初に近江国の浅井長政に仕えたとされます。いつかははっきりしませんが、元亀元(1570)年に織田・徳川軍と浅井・朝倉軍が戦った有名な姉川の戦いで浅井軍に属したとされています。
姉川の戦いの時、高虎は15歳です。数え年なので、今なら14歳の中学生です(この後も年齢は数え年で記します)。今の日本では考えられないですね。
高虎の初転職―ケンカが理由―
さて、高虎は滅亡寸前の浅井家を見限ったように見えますが、実は同僚をケンカで斬り殺し、追手に捕まる前に逃げ出したと言われています。まぁ、同僚を斬り殺す時点で褒められたものではありませんが…。
これは浅井家が滅亡する前年とされ、高虎17歳です。この後も同じような事件を起こします。勿論良くないことですが、高虎も人間だということを感じますね。
なお、世間では浅井家が滅亡して高虎が浪人になったと書かれている場合も見かけます。しかし、『高山公実録』では浅井家滅亡前にケンカが原因で逃げ出したとされています。
2人目の主君―またしてもケンカで退職―
次に仕えたのは、同じ近江国の阿閉淡路守(貞征か)です。浅井家を飛び出したのと同じ年です。1年ほど居たようですが、ここでも同僚を殺害して阿閉家を去ります。高虎18歳頃です。
時代も時代で、若い頃とは言え、浅井家・阿閉家と続けて殺人事件…高虎怖いですね(笑)
さぁ、2回連続でケンカで職を失った高虎(←自分のせいですが)。今後どうなっていくのでしょうか?
3・4人目の主君―転職回数にカウントしていいの?―
3人目の主も同じ近江国の磯野員昌です。員昌は浅井氏に属していましたが、織田信長の勢力が及ぶと信長に属しました。高虎はここで初めて80石を与えられます。
員昌は信長の甥の信澄を養子に迎え、後に代替わりしたとされ、高虎も引き続き信澄に仕えます。この信澄が4人目の主君として数えられています。
ん?ちょっと待て・・・社長が交代したら「転職」になるんですか?代替わりならば、高虎の意志で主君を変えたわけではありません。
信澄を高虎の転職1回にカウントするのは明らかに変では?磯野家(織田信澄家)として主君は1人(1家)としてカウントすべきでは?
高虎、初めて主君を見限る
高虎はこの後、やっと「普通」の転職を決断します。
信澄のもとで戦いで活躍した結果、役職は出世しますが、80石のままでした。これでは新しい役を務めるのは経済的に難しいということで信澄に加増を願い出ましたが、却下され、信澄のもとを去ります。
少し違うかもしれませんが、役職が上がったのに給料がそのままだったということです。そこで、もっと自分の能力を買ってくれるところへ転職することにしたんでしょう。しかし、多分次の仕事(主君)は決まってなかったかと…。高虎20~21歳頃です。
理想の上司?豊臣秀長との出会い
そして、5人目(信澄を4人目とするのは納得いきませんが、ややこしいので、通説どおり5人目にしときます)にして、高虎の人生を大きく変えることになる木下秀長(後の豊臣秀長。秀吉の弟。)に仕えます。時に天正4(1576)年、高虎は21歳です。ここからは秀長が亡くなるまで15年(高虎36歳まで)仕え続けます。
21歳までは職を点々としたが、その後の会社には社長が亡くなるまで15年勤めた。これってそんなに非難されますか?しかも、主君を見限った転職ばかりではありません。
ちなみに、秀長が亡くなった後は養子の秀保が家を継ぎ、高虎は引き続き仕えます。社長の没後も会社に残ったわけです。
ここまで(磯野員昌→織田信澄も1回と数えれば)主君を4回変えて秀長に仕えるに至りました。先に答えを言うと、世間では、秀長→秀保が5回目、秀保→豊臣秀吉が6回目、秀吉→徳川家康が7回目の転職というようにカウントされます。
気づきましたか?何か変です。次回の更新までに何が変なのか、考えてみてくださいね。
《参考文献》
- 阿部猛・西村圭子編『戦国人名事典コンパクト版』(新人物往来社、1990年)
- 『高山公実録』上巻・下巻(清文堂出版、1998年)

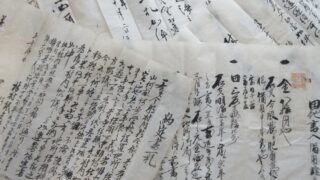

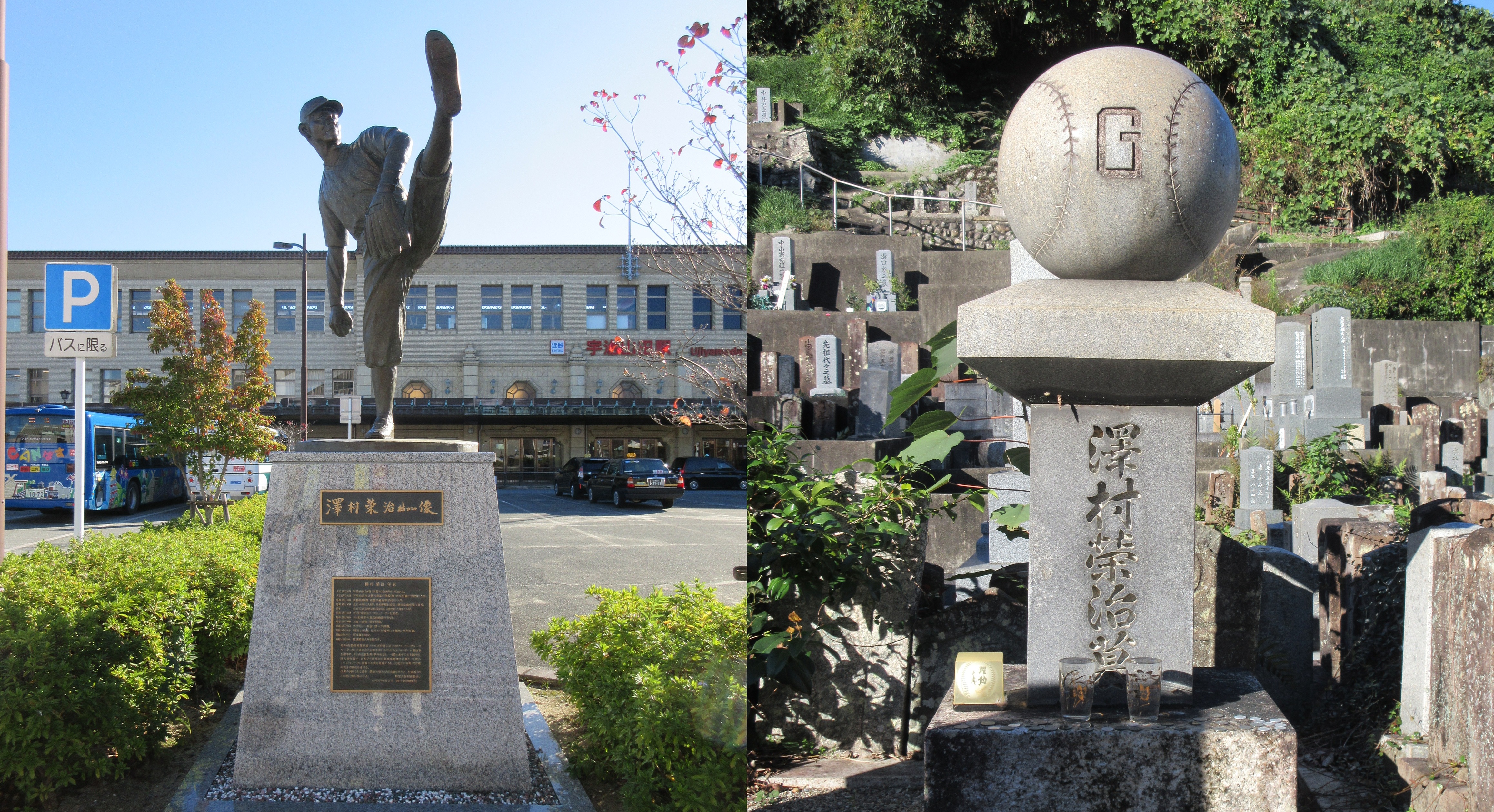
コメント