前回は、公儀普請(幕府が大名を動員して行った城の普請)に関して、幕府が大名に対して行った配慮として、大名の疲弊等を理由に普請役(大名が城の普請に動員されること)を一定期間見送ったことを見てきました。
今回は他に幕府が行った配慮である、大名への米の支給と、大名の事前準備が無駄になった場合の支援について見ていきます。
また、そもそもなぜ公儀普請を行ったのかについても解説します。
普請を行う場合に大名に米を支給
前回に引き続き、公儀普請を実施する時に幕府が行った配慮である、大名への米の支給を見ていきましょう。
前回少し書いたように、元和5(1619)年9月16日に大坂城の普請役が西国の大名に賦課されました。
普請は翌元和6年に行われます。この時、幕府は普請役を賦課した大名に対して、起工とほぼ同時期に米を支給しています。
また、寛永元(1624)年・同5年の大坂城普請でも、幕府は大名へ米を支給しています。
この米の支給は、普請が終わった後の褒美とは別物です。起工とほぼ同時に支給していることは、可能な限り大名の負担を軽減するためと考えられています。
ただ、これで大名の負担がほぼゼロになったかというと、そうではありません。なぜなら、支給された米は大名の役高(領地の石高に応じて決められている、動員する人数等)に応じた量だったからです。大名がそれ以上の人数を自主的に動員すれば、大名は幕府から支給された米以上の支出が必要となります。
例えば、前回書いたように、細川家は普請が遅れないようにするため、日雇労働者を何人でも雇うように家臣へ指示していました。もし、ある大名の石高に応じた動員人数(役高)が1,000人であれば、幕府から支給されるのは1,000人分の米です。しかし、大名が自主的に3,000人を動員すれば、差引き2,000人分の米は大名の自腹になります。
実際に、寛永5年の大坂城普請における鍋島家の例では、幕府から支給された米は、鍋島家の支出の1割程度にしかなりませんでした。
これを見ると、幕府からの米の支給が大名にとってどれだけ恩恵に感じたかはわかりません。しかし、幕府は求めたのは石高に応じた動員であり、求めた人数分の米は支給しています。十分と言えば十分です。必要と言った以上に大名が自主的に動員した人数分まで面倒を見るわけにもいかないのでしょう。
ん?ちょっと待てよ?米を支給するぐらいなら、そもそも公儀普請をしない、又は幕府が直接人を雇って実施すればよいではないか、と思いませんか?それが、そうもいかないのです。
公儀普請の必要性
当時の幕府は、まだまだ大名に対して絶対的な権力を手にしていたとは言い切れない状態でした。本来は将軍秀忠の命令で大名を繰り返し戦いに動員することで、将軍の軍事指揮権のもと、将軍と大名の力関係をはっきりさせることができたでしょう。しかし、大坂の陣以降、大きな戦いは無くなりました。
そこで、戦いへの動員に代わるものとなったのが公儀普請への動員だったのです。大名は、幕府の「御恩」(領地の安堵)に対して、戦いの場で「奉公」する代わりに、普請役を担うことで「奉公」したのです。
幕府は、戦いへの動員に代わるものとして普請役を大名に賦課し、大名に対し優位な地位を確立させていく必要がありました。そのため、大名へ米を支給してまで公儀普請を実施したのです。
しかし、前述のように実際は大名が自主的に多くの人員を動員したため、大名の財政は逼迫していくことになるのですが・・・。
また、米の支給といった支援策とは異なりますが、別の幕府の配慮が窺える事例もあります。
①公儀普請と重複する負担を回避・軽減
この元和6(1620)年の大坂城普請実施期間中において、幕府は・・・
- 秀忠の子・家光と忠長の元服・任官のための上洛を、普請による大名の苦労を理由に中止。
- 秀忠の娘・和姫入内(朝廷への嫁入り)に係る、大名からの祝儀の献上物を軽い物に設定。細川忠興は、これを秀忠の大名に対する「いたハり(労り)」と表現しています。
このことから、公儀普請の負担と重複して諸大名に過剰な負担が生じないように配慮していたことがわかります。
②財政難の大名は動員よりも軽い役を担わせる
土佐藩山内家が財政難で、公儀普請に人数を動員することが難しくなった時がありました。この時、幕府は山内家が材木を供出することで動員に代える(動員を免除する)ことを認めました。これは、幕府が山内家を救済することが目的とされています。
大名の事前準備が無駄になった場合の支援
最後に、大名の準備が無駄になってしまった時の幕府の対応を見てみましょう。
先ほどの米の支給でも出てきた、元和6年の大坂城普請です。これは元和5(1619)年9月16日に大坂城の普請役が西国の大名に賦課され、翌6年に実施されたものです。
実は普請役が賦課される前々年の元和4年6月には、元和6年に「江戸城」の普請が実施されるとの噂が流れています。この情報をもとに、諸大名は江戸に近い石材産地であった伊豆国で石材を確保し始めました。公儀普請が決定した時に速やかに取り掛かることができ、かつ、他の大名よりも良い石を切り出す場所を確保するためです。
しかし、噂から約1年後の元和5年8月、西国の大名は江戸城ではなく大坂城普請を担うことに変更されてしまいます。
大坂城の普請であれば、遠く離れた伊豆国で石材を確保しても、運ぶのが大変です。大坂城の場合は、例えば瀬戸内海の小豆島等の近場で石材を確保できます。江戸城普請に使うつもりで、西国大名が伊豆国で確保していた石材は無駄になってしまいました。大名にとってはこの石材を何とかしなければなりません。
そこで、例えば細川氏は元和6年1月に、確保中の石材を町人に売却することを決定しました。これは、幕府が江戸城普請の石材調達を町人に命じた(町人が石材を確保し始めると想定された)ためです。
そのような中、またしても自主的な動きをする大名が出てきます。
今まで、家康の配慮にもかかわらず隠居所の普請を買って出る大名や、必要以上の人数を普請に動員する大名がいましたね。ここでも同じような動きと言えるでしょうか。
今回は、外様大名である加藤嘉明(西国大名)が、確保していた石材を秀忠に献上します。これに秀忠が機嫌を良くしたため、諸大名による石材献上が行われる見込みとなりました。
ここで秀忠は、献上された石材を大名からの「借用」と位置付け、借料を支払う意向を示します。実際は石材を城の石垣に使ってしまえば返却などできませんから、借料を払って永久に借りる=実質の買取りです。
これが秀忠の配慮であることは、元和6年2月25日付で、細川忠利が家臣の長船十右衛門へ宛てた(実質は長船を通じて忠興に披露される)書状からわかります。この書状には次のような事が書かれています。
- 幕府の勘定頭・伊丹康勝から、石材を全て幕府へ差し出すように連絡があった。
- 秀忠は大坂城普請賦課と江戸城普請用石材を差し出させたことが大名の負担にならないように、借料を支払う方針を示した。
このように、幕府は石材調達を諸大名ではなく町人に命じ、大名が確保していた石材を実質的に購入することで江戸城普請に備えたのです。これも秀忠の配慮の一環と考えられています。
おわりに
どうでしたか?幕府が大名に公儀普請を課したのは、確かに幕府の優位性を高めるためでした。しかし、それは幕府が大名に与えた「御恩」に対する「奉公」と考えられており、決して幕府の一方的な意向で大名を使役したのではありません。
大名側も進んで普請役を担うことを望んだり、必要な石材を献上したりする等、それはまるで戦いで我先に戦功を挙げようとする姿と重なるように思います。
そんな大名が普請役で倒れてしまわないように、幕府は様々な配慮・支援を行い、大名が存続できるようにしていました。
幕府が大名を弱らせようとして普請役を課したのではなく、幕府と大名それぞれにとって、普請というものは(理由は違えど)必要とされたものだったのではないでしょうか。
《参考文献》
- 川路祥隆「徳川秀忠政権の公儀普請にみる対大名政策」(『日本歴史』916号、2024年9月)

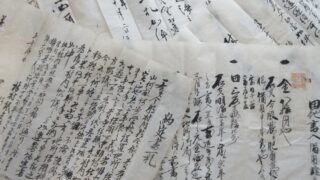
コメント